29
 「A
Scene In Between」 Sam Knee
「A
Scene In Between」 Sam Knee
副題"Tripping Through The Fashins of UK Indie Music 1980-1988"。2013年初刊の80年代UKインディバンドの写真カットを中心としたムック本の、今年出た改訂版。Johnny Marr(The Smiths)、Debbie Googe(MBV)、Lawrence(Felt)のインタビューも掲載。ポスト・パンク後の在インディーレーベル・ギターポップ?バンド群がいろいろ載ってて、頁めくっていくや、自分も学生時代に戻ってしまう。Orange Juiceから始まり、J&MC、Spacemen3、Loop...Vaselines。懐かしい名前もあれば知らないバンドも。インタビューも面白く、ファッションの話の合間に当時のバンドシーンやカルチャーシーンの話など。Orange Juice、The Fall、Feltの名前はよく出てくる。以前、映画「Shoplifters...」を観たときの、これじゃない感...あれは米国の話だったからで、英国ではこれらサブカルチャーシーンが違う意味を持ってて、それと切っても切れない音楽だしファッションだということが伺える。とにかく、パラパラ眺めてるだけで愉しいのです。
もう長いこと新型コロナウイルス感染の話は書いてこなかったけど、現在新型株による第7波の真っ最中。日本の検査陽性者は世界一になっている、そんな昨今。今週米国出張中の当社VIPの方々の一部は米国内の拠点訪問をするみたいだけど、米国内線で感染しないのだろうか...。ちなみに、直属本部長女史が今日予定してたインド関係の会議は、インドから帰国して参加予定の先方が、日本で感染してしまって来週に急遽延期になったとか。
24
 「百億の昼と千億の夜[完全版]」萩尾望都
「百億の昼と千億の夜[完全版]」萩尾望都
カラーページも復刻での豪華版再刊。光瀬龍と萩尾望都の関連エッセイと年表を収録。言わずもがなの1977-78年に週刊少年チャンピオンで連載された日本SF漫画と言わず漫画史に残る傑作。もちろん光瀬龍氏の日本SF漫画史に残る金字塔的名作が原作。終盤の非形而的な展開をビジュアルに表現した頁の数々は今読んでも色褪せることはない。美麗なカバーも素晴らしく、SFモノなら手元に置いとくべき一冊。巻末の今年5月に録った萩尾氏のインタビューは、SFに絞った濃密なもので、先生の口から出てくる海外SFの作品名に相槌を打つこと頻り...というか、自分のSF観に多大な影響を与えてもらっていることを改めて意識したり。
いつものように長女とでかける週末の堀口珈琲。彼女から重い決断を聞く。まあいろいろあるが、区切りは必要。
23
 「星のパイロット」笹本祐一
「星のパイロット」笹本祐一
カリフォルニアにある民間航空宇宙会社を舞台にしたシリーズの再文庫化。初出は1997年のソノラマ文庫、2012年に朝日ノベルズ、今回新刊が出るのにあわせて加筆修正版が東京創元社から。宇宙飛行士に欠員の出たスペースプラニング社の新入社員は日本人の女性パイロット、個性的な社員達と知り合いながら最初のミッションへ挑む...というメンバー紹介編。クラシックな軍用機や航空機(現ウクライナ戦役で破壊されたAN225も登場)が宇宙機を軌道に打ち上げる様を丁寧に描いていて、その筋の愛好家には堪らんのだけど、その雰囲気が好きでなければテクニカルな描写は退屈かも。
18
 「銀河帝国の興亡3 回天編」アイザック・アシモフ(鍛冶靖子
訳)
「銀河帝国の興亡3 回天編」アイザック・アシモフ(鍛冶靖子
訳)
前巻のミュール編を回収して、その流れで第二ファウンデーションの秘密に迫る最終巻。内容の記憶は殆どなく、アシモフ得意のミステリ展開を楽しんで読めた。最後ぼやかしてた印象が記憶だったんだけど、かなりガチの謎解きモノでオチもちゃんと付けてたのね。もともと連載に発展したシリーズなので、3巻通しての流れは俯瞰してみると取って付けた感もなくはないが、40年代に書かれた本書が今読んでもむしろ現代的というのも面白いんじゃないだろうか。
17
 「新しい時代への歌」サラ・ピンスカー(村山美雪
訳)
「新しい時代への歌」サラ・ピンスカー(村山美雪
訳)
原題"A Song For A New Day"。米国でイベント会場を標的にした同時多発テロが起こり以来公共の場での集会が禁止される、時を同じくして全身に膿疱が発症するウイルスによるパンデミックが起こり...、テロ発生のその日最後のリアル・ライヴを開催した伝説のロックシンガー/ルース、一方で"アフター"世代でVRネイティブなローズマリー、タッチレス社会になり生活のみならず文化的インフラも巨大IT企業に依存しきっている米国で、ライヴ音楽配信ビジネスを軸に、旧新世代の二人の人生が交錯する。2019年原著初版の本書は当然のように予言の書として米国でも日本でも(邦訳初版は21年9月)高く評価されたわけだけど、新株での感染拡大が波となって途切れないまでもコロナ禍に慣れてしまいつつある(という意味ではアフターコロナに入りつつある)今日読むと、コロナ禍最中とは違うメッセージが見えてくる。途中まで青春モノというかヤングアダルト向けな感触だったりもしたんだけど、「スノウ・クラッシュ」から20年ならではな骨太な近未来ビジョンが垣間見え、ほろ苦くも希望を感じさせるラストも巧い。ところどころ出てくるミュージシャンや曲名が、話の展開にハマってるところも楽しい。ポニーテールが印象的に描かれるルースだけど、イメージは80年代のクリッシー・ハインドかな~。
10
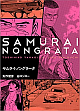 「サムライ・ノングラータ」矢作俊彦、谷口ジロー
「サムライ・ノングラータ」矢作俊彦、谷口ジロー
ハードカバーで復刊されてたのに気づいてポチる。90年~91年の連載で、いわゆるバブル末期・湾岸戦争期の雰囲気は、「気分はもう戦争」の10年後に描かれた矢作式ハードボイルドならではの面白さに満ちてて、じっくり味わいながら再読する価値のある傑作。谷口氏の画業録上は傑作には挙がらないだろうけどね。携帯電話が普及してないしダイアル回線でネット接続してた時代の国際政治経済もの。最終話は今はなき超大物も登場する。それこそスターリンクが戦争に使われる現代で、同じような物語(現在の目からすればある種のゆるさがある)にはならないだろうけど、日本人についての国際政治背景のハードボイルド劇画を、新たな世界戦争の時代である2020年代に読みたい気になっているので、誰か矢作氏をその気にさせてほしい。(「気分はもう戦争3 (だったかもしれない)」みたいな断片がたまに出てくるでもかまわないので。)
07
 「A
Scene In Between」 Sam Knee
「A
Scene In Between」 Sam Knee副題"Tripping Through The Fashins of UK Indie Music 1980-1988"。2013年初刊の80年代UKインディバンドの写真カットを中心としたムック本の、今年出た改訂版。Johnny Marr(The Smiths)、Debbie Googe(MBV)、Lawrence(Felt)のインタビューも掲載。ポスト・パンク後の在インディーレーベル・ギターポップ?バンド群がいろいろ載ってて、頁めくっていくや、自分も学生時代に戻ってしまう。Orange Juiceから始まり、J&MC、Spacemen3、Loop...Vaselines。懐かしい名前もあれば知らないバンドも。インタビューも面白く、ファッションの話の合間に当時のバンドシーンやカルチャーシーンの話など。Orange Juice、The Fall、Feltの名前はよく出てくる。以前、映画「Shoplifters...」を観たときの、これじゃない感...あれは米国の話だったからで、英国ではこれらサブカルチャーシーンが違う意味を持ってて、それと切っても切れない音楽だしファッションだということが伺える。とにかく、パラパラ眺めてるだけで愉しいのです。
もう長いこと新型コロナウイルス感染の話は書いてこなかったけど、現在新型株による第7波の真っ最中。日本の検査陽性者は世界一になっている、そんな昨今。今週米国出張中の当社VIPの方々の一部は米国内の拠点訪問をするみたいだけど、米国内線で感染しないのだろうか...。ちなみに、直属本部長女史が今日予定してたインド関係の会議は、インドから帰国して参加予定の先方が、日本で感染してしまって来週に急遽延期になったとか。
 「百億の昼と千億の夜[完全版]」萩尾望都
「百億の昼と千億の夜[完全版]」萩尾望都カラーページも復刻での豪華版再刊。光瀬龍と萩尾望都の関連エッセイと年表を収録。言わずもがなの1977-78年に週刊少年チャンピオンで連載された日本SF漫画と言わず漫画史に残る傑作。もちろん光瀬龍氏の日本SF漫画史に残る金字塔的名作が原作。終盤の非形而的な展開をビジュアルに表現した頁の数々は今読んでも色褪せることはない。美麗なカバーも素晴らしく、SFモノなら手元に置いとくべき一冊。巻末の今年5月に録った萩尾氏のインタビューは、SFに絞った濃密なもので、先生の口から出てくる海外SFの作品名に相槌を打つこと頻り...というか、自分のSF観に多大な影響を与えてもらっていることを改めて意識したり。
いつものように長女とでかける週末の堀口珈琲。彼女から重い決断を聞く。まあいろいろあるが、区切りは必要。
 「星のパイロット」笹本祐一
「星のパイロット」笹本祐一カリフォルニアにある民間航空宇宙会社を舞台にしたシリーズの再文庫化。初出は1997年のソノラマ文庫、2012年に朝日ノベルズ、今回新刊が出るのにあわせて加筆修正版が東京創元社から。宇宙飛行士に欠員の出たスペースプラニング社の新入社員は日本人の女性パイロット、個性的な社員達と知り合いながら最初のミッションへ挑む...というメンバー紹介編。クラシックな軍用機や航空機(現ウクライナ戦役で破壊されたAN225も登場)が宇宙機を軌道に打ち上げる様を丁寧に描いていて、その筋の愛好家には堪らんのだけど、その雰囲気が好きでなければテクニカルな描写は退屈かも。
 「銀河帝国の興亡3 回天編」アイザック・アシモフ(鍛冶靖子
訳)
「銀河帝国の興亡3 回天編」アイザック・アシモフ(鍛冶靖子
訳)前巻のミュール編を回収して、その流れで第二ファウンデーションの秘密に迫る最終巻。内容の記憶は殆どなく、アシモフ得意のミステリ展開を楽しんで読めた。最後ぼやかしてた印象が記憶だったんだけど、かなりガチの謎解きモノでオチもちゃんと付けてたのね。もともと連載に発展したシリーズなので、3巻通しての流れは俯瞰してみると取って付けた感もなくはないが、40年代に書かれた本書が今読んでもむしろ現代的というのも面白いんじゃないだろうか。
1月以来の高尾山。10時過ぎ起床の際には疲れ溜まってるし今日は無理かなーと思ったものの晴れ空を見て、行くしかねーなと重い腰を上げた。高尾山口着12時過ぎ、人出はそこそこ、六号路を選ぶ。ところどころの路傍の花と、場所によっては轟々と鳴る沢沿いを登る。森の中は少し気温は低めだけど、濃密な湿度。山頂到着13:15、持ってきたカツサンドを食べて、稲荷山コースで下山。14:30前に清滝駅、ソフトクリーム食べて帰宅。2時間24分、8.04km、消費1,235kcal。森の中は楽しい。来てよかった。
16 「新しい時代への歌」サラ・ピンスカー(村山美雪
訳)
「新しい時代への歌」サラ・ピンスカー(村山美雪
訳)原題"A Song For A New Day"。米国でイベント会場を標的にした同時多発テロが起こり以来公共の場での集会が禁止される、時を同じくして全身に膿疱が発症するウイルスによるパンデミックが起こり...、テロ発生のその日最後のリアル・ライヴを開催した伝説のロックシンガー/ルース、一方で"アフター"世代でVRネイティブなローズマリー、タッチレス社会になり生活のみならず文化的インフラも巨大IT企業に依存しきっている米国で、ライヴ音楽配信ビジネスを軸に、旧新世代の二人の人生が交錯する。2019年原著初版の本書は当然のように予言の書として米国でも日本でも(邦訳初版は21年9月)高く評価されたわけだけど、新株での感染拡大が波となって途切れないまでもコロナ禍に慣れてしまいつつある(という意味ではアフターコロナに入りつつある)今日読むと、コロナ禍最中とは違うメッセージが見えてくる。途中まで青春モノというかヤングアダルト向けな感触だったりもしたんだけど、「スノウ・クラッシュ」から20年ならではな骨太な近未来ビジョンが垣間見え、ほろ苦くも希望を感じさせるラストも巧い。ところどころ出てくるミュージシャンや曲名が、話の展開にハマってるところも楽しい。ポニーテールが印象的に描かれるルースだけど、イメージは80年代のクリッシー・ハインドかな~。
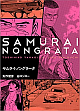 「サムライ・ノングラータ」矢作俊彦、谷口ジロー
「サムライ・ノングラータ」矢作俊彦、谷口ジローハードカバーで復刊されてたのに気づいてポチる。90年~91年の連載で、いわゆるバブル末期・湾岸戦争期の雰囲気は、「気分はもう戦争」の10年後に描かれた矢作式ハードボイルドならではの面白さに満ちてて、じっくり味わいながら再読する価値のある傑作。谷口氏の画業録上は傑作には挙がらないだろうけどね。携帯電話が普及してないしダイアル回線でネット接続してた時代の国際政治経済もの。最終話は今はなき超大物も登場する。それこそスターリンクが戦争に使われる現代で、同じような物語(現在の目からすればある種のゆるさがある)にはならないだろうけど、日本人についての国際政治背景のハードボイルド劇画を、新たな世界戦争の時代である2020年代に読みたい気になっているので、誰か矢作氏をその気にさせてほしい。(「気分はもう戦争3 (だったかもしれない)」みたいな断片がたまに出てくるでもかまわないので。)
紆余曲折のすえ、通帳印鑑は父の交際相手に送ることになり、この機会にいろいろ手を引くことにして気分的にはスッキリ。これで実家と往復することも当分なさそう。母の三回忌法要の出欠確認はがきをネットで発注するなど。
03
2日土曜日に当社の展示を見に横浜へ。5月に行った同じ領域の欧州学会大会とつい比較してしまう。少し居たたまれなくなり早めに会場を出て、Wと待ち合わせの汐留へ。5時予約の1時間弱前に着いてしまったので、どこか時間潰せるところないかと探してみたけど何もなく、結局早めにお店に入って寛いでW待ち。スペイン料理とワインは美味しく、8時頃に東京ビッグサイト近くの宿へ。呑み直したあとに爆睡、朝食、予定してた展示訪問2日目はやめ帰宅。先先週末に買いに行った、謝罪会見トレーニング用の黒スーツが届いていた。