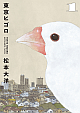31
 「バクトリア王国の興亡」前田耕作
「バクトリア王国の興亡」前田耕作
副題"ヘレニズムと仏教の交流の原点"、1992年初版を2019年に一部加筆・表記見直しして文庫化したもの。現アフガニスタン北部からインド西部に渡るバクトリア、その隣の現イランであるパルティアの古代史。アケメネス朝盛衰からアレクサンドロスによるギリシア文化のインダス河までの版図拡大とその後の分裂、遠くギリシア・シリアを見ながら栄枯盛衰を繰り返し変遷していくヘレニズム世界、その東端であるバクトリア、ゾロアスター教の地ながら仏教の影響を受け、ユーラシア東部での匈奴の動きに端を発した民族移動で消滅していく様子。ローマ時代初期まで、「ラウィーニア」の頃の世界史。広範な地域をまたがる歴史を時系列だけで整理はできないので、地域を行きつ戻りつ...加えて人物名がわかりにくく(同じまたは類似の人名が錯綜する)字面を追うだけでは詳細理解できないけど、大きな歴史の流れと主要な人物、地勢についてはイメージができた。中央アジアの仏教都市群とペルシア・ギリシアを繋ぐ地理的感覚が埋まったので、古代世界の広がりが今までよりも掴めてきた気がする。ここからさらに、宗教・文化が混交するなヘレニズム世界が、イスラム化され、今日現在は原理的イスラム主義アフガンに為る経緯を理解したい。まずはゾロアスター教についての読み物を。
そういえば、著者の前田耕作氏はバシュラール「火の精神分析」の訳者でもいらっしゃるとのこと。自分の中で色々と繋がる。
30
 「The
Art and Soul of DUNE」タニア・ラポイント(阿部清美 訳)
「The
Art and Soul of DUNE」タニア・ラポイント(阿部清美 訳)
ドゥニ・ヴィルヌーヴDUNEの設定・アートの解説本、邦訳版。サンドワームの壁画をあしらった箱に入った、重厚な装丁。紙質もよく、鍵となる設定について丁寧な解説とビジュアル。色々とエピソードも書かれていて、読み応えもある(シャーロット・ランプリングがホドロスキー版でレディ・ジェシカ役でオファー貰ってたとは知らなかった...、「ホドロフスキーの...」でそんな話してたっけ?)。映画館では人物・用語説明と評論家の解説(添野知生氏の映像化の歴史を書いたものくらいしか内容がない)からなるパンフレット以外の物販もなく物足りない人々には、嬉しいギフトじゃないだろうか。6,600円の価値はあると思う。
白土三平氏死去の報。
24
 2回目のIMAX「DUNE」。TOHOシネマズ新宿のIMAXレーザーで中央最前列。この間より音響はキツくなく、今回は微細な音(例えば、墜落したオーニソプターの中で微かになるノイズとか)も意識できた。ほんの数日前に観たばかりなのに、没入感は半端ない。現場観察者視点の撮り方が秘訣な気がする。大画面を使った俯瞰の映像も効果的。前回のエンドクレジットで気がついたシャーロット・ランプリング、改めて観ると存在感凄い。ベールの向こうの視線と声だけで圧倒的。字幕は若干説明的な言い回しになってるところがあるけど、含意がこもった端的な台詞も素晴らしいので、その辺も楽しんでほしいなあ...。IMAXで観れるうちにもう一回は行きたい。
23
2回目のIMAX「DUNE」。TOHOシネマズ新宿のIMAXレーザーで中央最前列。この間より音響はキツくなく、今回は微細な音(例えば、墜落したオーニソプターの中で微かになるノイズとか)も意識できた。ほんの数日前に観たばかりなのに、没入感は半端ない。現場観察者視点の撮り方が秘訣な気がする。大画面を使った俯瞰の映像も効果的。前回のエンドクレジットで気がついたシャーロット・ランプリング、改めて観ると存在感凄い。ベールの向こうの視線と声だけで圧倒的。字幕は若干説明的な言い回しになってるところがあるけど、含意がこもった端的な台詞も素晴らしいので、その辺も楽しんでほしいなあ...。IMAXで観れるうちにもう一回は行きたい。
23
 「ロシア正教の千年」廣岡正久
「ロシア正教の千年」廣岡正久
1993年にNHKブックスから出版されたものを2020年に20頁の補足を巻末に加えて講談社学術文庫から出したもの。ひと月前に読んだ「中世の異端者たち」からの脱線というところもあるし、東方教会にはこの前のドイツ駐在から興味を持ってきたので、その再燃...てとこもある。東方教会史千年を1冊に...という期待は外れ、折しもペレストロイカからソ連崩壊の中でロシア正教会四百年祭を目の当たりにした著者が、その勢いでロシア正教会の生い立ちとソヴィエト時代の受難と今日(当時)を著したもの...という内容。反ソヴィエトの筆致強く、またロシア正教会への愛着故か、後半のストーリーに合わせて序盤から語られていくので、歴史を理解するという意味では眉唾。そもそも歴史を書いた側の記述に寄り過ぎではないか?という不信を持ちながら読んでいた。今回文庫化のために追加された補稿部分は、冷静な論考がされているのが対照的。まあ、この辺をきちんと書くのは色々難しい気はするけど。
22
 「DUNE」ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督
「DUNE」ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督
今日明日と終日の社内研究発表会は、リモート開催...なので、午後から出社しzoomインのまま、その足でオフィスの入ってるビル階下にあるTOHOシネマズでIMAX「DUNE」。ヨルダン、アブダビ、ノルウエーで撮影された映像は大画面で観ることを前提としたスケール。衣装から室内装具調度品、ガジェットに宇宙船、全てに細心に造り込まれていて、非の打ち所が見当たらない。オーニソプターも、大活躍で嬉しい(傍にいると耳栓要りそうだけど)。IMAXの音響になれるのに一寸時間がかかったけど、慣れてくると音圧も気持ち良いし、無音を使った演出には思わず身動き止めた。ストーリー自体はよく知っているので、驚きも混乱もないんだけど、逆に知ってるからこそ惹き込まれる演出に思えたし、過去2回の映像化を踏まえて観るファンをねじ伏せようと言わんばかり力の入り様には脱帽。「物語はこれから」なので、最後まで見届けてどういう評価が下るのか、楽しみ。
折しもApple TV契約して「ファウンデーション」観始めたところなんだけど、しばらく「DUNE」の余韻に浸りたく、少し間を空けたほうがいいかなあ...なんて思っている。
20
 「高丘親王航海記」近藤ようこ(澁澤龍彦
原作)
「高丘親王航海記」近藤ようこ(澁澤龍彦
原作)
2020年に第一巻が出た漫画化版、今週出た第四巻で完結した。原作に忠実、だけどキャラクターが近藤ようこの線で描かれることで、テキストを追うのとは異なる時間で話が動いているように感じた。原作の比較的シンプルだけど情報密度の高い(読み解こうとすると深さに驚く)異世界紀行とはまた違う、親王の感情の動きがより際立つ死生観を中心にしたストーリー。絵で表現された表情や視線が、空間的だったり内面的な広がりを生んでいることによるのだろう。読了後、しばし余韻に浸って動けず。
読んだ勢いで、ビリケンギャラリーでやっている原画展「南方奇譚」を見に行ってきた。在廊していた近藤先生にお願いして、第四巻の最終ページ(「完」の文字の横)にサインを戴く。明日で最終日ということもあって、お忙しそうでした。その後、ここまで一人で出てくることもなかなかないので、久しぶりの月光茶房。お忙しそうなところ、カウンターの末席にお邪魔してコーヒーを一杯。表参道は人出いっぱい。
10
 「台湾 四百年の歴史と展望」伊藤
潔
「台湾 四百年の歴史と展望」伊藤
潔
1993年初版、自分が今回読んだのは26版(2020年)なので、長く読みつがれているのがよくわかる。実際、ポルトガルに"発見"されてから刊行直前まで(李登輝総裁二期目)の台湾史を11章にわけてわかりやすくまとめたもので、「自転車泥棒」「台湾海峡」を思い出しながら、彼の地の歴史大河が俯瞰できる。 著者は1937年台湾生、在命なら父と同じ歳(著者は2006年に逝去)..日本統治時代以降の語り口には我が親世代からのメッセージのようなものも感じる。短いが非常に思いが詰まった"あとがき"も、胸に迫る。「台湾海峡」には二・二八事件や戒厳令時代には触れられていないんだけど(「自転車泥棒」では二・二八事件は出てくる)、その時代をオープンに語れるまでにはなってないんだろうなあ...などと未だ続く複雑な政治・社会状況にも少し思い描いたり。断片的だった"台湾"の印象が、繋がって大きく更新されたように思う。奇しくも習近平の国家統一についての演説のタイミング、今後の動向から目が話せない。
09
 「台湾海峡 一九四九」龍應台(平野
健太郎 訳)
「台湾海峡 一九四九」龍應台(平野
健太郎 訳)
原題「大江大海1949」、台湾での初版刊行は2009年、邦訳は2012年刊。「自転車泥棒」を切欠に、太平洋戦争前後のことを読みたくて...ということだったんだけど、本書によって、日中戦争から終戦..国共内戦の中で苛まれる人々について、さらに深く当時を知ることになった。大河ドキュメンタリーというわけではなく、本書を書くためのプロジェクトで収集した膨大な証言をもとに構成しており、著者の家族の話から始まって、国民党軍・解放軍の軍属、兵卒、日帝軍兵として戦った台湾人、その家族、学生、そして日帝軍人、豪・米兵などなど一人ひとりのストーリーに触れていくことで、混沌とした戦中戦後の台湾...のみならず中華民族の悲哀が浮かび上がる。教科書的な後付解釈による時代の整理とは異なる視点は、紋切り型の民族や国家の見方に対するアンチテーゼになってて、読み進めながら襟を正しつつ、近現代のアジアへの興味が湧き上がってきた。
突然の戦後を迎えたアフガニスタンを彷彿とさせるし、文化統制を強める昨今の習政権など、10年前の本だけど、リアルに今に対する示唆にも富んでいる。邦訳にあたって訳者による構成の調整などが施されたと訳者あとがきにあるが、丁寧な翻訳に感謝。良い本に巡り会えた。
03
 「松本大洋本」小学館(漫画家本vol.4)
「松本大洋本」小学館(漫画家本vol.4)
2018年刊のムック本。本人の長尺インタビュー、対談、評論、トリビュートに単行本未収録短編3作。amazonのオススメ。単行本未収録作も含めたこの当時までの作品リストを見ると、まあそこそこ読んでる気がする。すべてが好きな作品ではないし、少なくとも「花男」までは画が巧いとも思ってなかったんだけど(当時は、嫌いじゃなかったし、面白い絵だなーと思っていた)、大友克洋に憧れて...だったとは思わなかったなー。夏目房之介が「間に合った作家・松本大洋」で論じてる漫画出版の90年代末からの衰退に関する示唆は「東京ヒゴロ」に繋がってる。インタビューや対談の回想にも繋がりが見えて、続けて読んで正解。
01
 「バクトリア王国の興亡」前田耕作
「バクトリア王国の興亡」前田耕作副題"ヘレニズムと仏教の交流の原点"、1992年初版を2019年に一部加筆・表記見直しして文庫化したもの。現アフガニスタン北部からインド西部に渡るバクトリア、その隣の現イランであるパルティアの古代史。アケメネス朝盛衰からアレクサンドロスによるギリシア文化のインダス河までの版図拡大とその後の分裂、遠くギリシア・シリアを見ながら栄枯盛衰を繰り返し変遷していくヘレニズム世界、その東端であるバクトリア、ゾロアスター教の地ながら仏教の影響を受け、ユーラシア東部での匈奴の動きに端を発した民族移動で消滅していく様子。ローマ時代初期まで、「ラウィーニア」の頃の世界史。広範な地域をまたがる歴史を時系列だけで整理はできないので、地域を行きつ戻りつ...加えて人物名がわかりにくく(同じまたは類似の人名が錯綜する)字面を追うだけでは詳細理解できないけど、大きな歴史の流れと主要な人物、地勢についてはイメージができた。中央アジアの仏教都市群とペルシア・ギリシアを繋ぐ地理的感覚が埋まったので、古代世界の広がりが今までよりも掴めてきた気がする。ここからさらに、宗教・文化が混交するなヘレニズム世界が、イスラム化され、今日現在は原理的イスラム主義アフガンに為る経緯を理解したい。まずはゾロアスター教についての読み物を。
そういえば、著者の前田耕作氏はバシュラール「火の精神分析」の訳者でもいらっしゃるとのこと。自分の中で色々と繋がる。
1週間前からの右眼の結膜下出血、白目半分を占める赤い血が引く気配がなく、通ってる整体院のお姉さんや同僚からも煩く言われるので眼科を受診。拡大して見てみると、外傷によるものらしいとのこと。「1週間してこの状態は出血多かったんでしょう、あと1週間は吸収されるのに掛かりそうですが、早めるなら点眼液出しますけどどうしますか?」...出してもらいました点眼液。周囲が煩いので早く無くなるといいなあ。
29
27
2015年9月にKicksterterでクラウドファンディングしたチタン製折りたたみ自転車が届いた。昨年7月には軽量パーツへのアップデートの受注があったり、今年に入って溶接部分の強度不足でリコールがあったりの紆余曲折はあったけど、6年は長いよねー。出社から帰宅晩飯後に開梱の儀。軽さに驚く。組み立ても簡単。早く乗りたい。
26 「The
Art and Soul of DUNE」タニア・ラポイント(阿部清美 訳)
「The
Art and Soul of DUNE」タニア・ラポイント(阿部清美 訳)ドゥニ・ヴィルヌーヴDUNEの設定・アートの解説本、邦訳版。サンドワームの壁画をあしらった箱に入った、重厚な装丁。紙質もよく、鍵となる設定について丁寧な解説とビジュアル。色々とエピソードも書かれていて、読み応えもある(シャーロット・ランプリングがホドロスキー版でレディ・ジェシカ役でオファー貰ってたとは知らなかった...、「ホドロフスキーの...」でそんな話してたっけ?)。映画館では人物・用語説明と評論家の解説(添野知生氏の映像化の歴史を書いたものくらいしか内容がない)からなるパンフレット以外の物販もなく物足りない人々には、嬉しいギフトじゃないだろうか。6,600円の価値はあると思う。
白土三平氏死去の報。
 2回目のIMAX「DUNE」。TOHOシネマズ新宿のIMAXレーザーで中央最前列。この間より音響はキツくなく、今回は微細な音(例えば、墜落したオーニソプターの中で微かになるノイズとか)も意識できた。ほんの数日前に観たばかりなのに、没入感は半端ない。現場観察者視点の撮り方が秘訣な気がする。大画面を使った俯瞰の映像も効果的。前回のエンドクレジットで気がついたシャーロット・ランプリング、改めて観ると存在感凄い。ベールの向こうの視線と声だけで圧倒的。字幕は若干説明的な言い回しになってるところがあるけど、含意がこもった端的な台詞も素晴らしいので、その辺も楽しんでほしいなあ...。IMAXで観れるうちにもう一回は行きたい。
2回目のIMAX「DUNE」。TOHOシネマズ新宿のIMAXレーザーで中央最前列。この間より音響はキツくなく、今回は微細な音(例えば、墜落したオーニソプターの中で微かになるノイズとか)も意識できた。ほんの数日前に観たばかりなのに、没入感は半端ない。現場観察者視点の撮り方が秘訣な気がする。大画面を使った俯瞰の映像も効果的。前回のエンドクレジットで気がついたシャーロット・ランプリング、改めて観ると存在感凄い。ベールの向こうの視線と声だけで圧倒的。字幕は若干説明的な言い回しになってるところがあるけど、含意がこもった端的な台詞も素晴らしいので、その辺も楽しんでほしいなあ...。IMAXで観れるうちにもう一回は行きたい。 「ロシア正教の千年」廣岡正久
「ロシア正教の千年」廣岡正久1993年にNHKブックスから出版されたものを2020年に20頁の補足を巻末に加えて講談社学術文庫から出したもの。ひと月前に読んだ「中世の異端者たち」からの脱線というところもあるし、東方教会にはこの前のドイツ駐在から興味を持ってきたので、その再燃...てとこもある。東方教会史千年を1冊に...という期待は外れ、折しもペレストロイカからソ連崩壊の中でロシア正教会四百年祭を目の当たりにした著者が、その勢いでロシア正教会の生い立ちとソヴィエト時代の受難と今日(当時)を著したもの...という内容。反ソヴィエトの筆致強く、またロシア正教会への愛着故か、後半のストーリーに合わせて序盤から語られていくので、歴史を理解するという意味では眉唾。そもそも歴史を書いた側の記述に寄り過ぎではないか?という不信を持ちながら読んでいた。今回文庫化のために追加された補稿部分は、冷静な論考がされているのが対照的。まあ、この辺をきちんと書くのは色々難しい気はするけど。
コタツが出た。
21 「DUNE」ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督
「DUNE」ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督今日明日と終日の社内研究発表会は、リモート開催...なので、午後から出社しzoomインのまま、その足でオフィスの入ってるビル階下にあるTOHOシネマズでIMAX「DUNE」。ヨルダン、アブダビ、ノルウエーで撮影された映像は大画面で観ることを前提としたスケール。衣装から室内装具調度品、ガジェットに宇宙船、全てに細心に造り込まれていて、非の打ち所が見当たらない。オーニソプターも、大活躍で嬉しい(傍にいると耳栓要りそうだけど)。IMAXの音響になれるのに一寸時間がかかったけど、慣れてくると音圧も気持ち良いし、無音を使った演出には思わず身動き止めた。ストーリー自体はよく知っているので、驚きも混乱もないんだけど、逆に知ってるからこそ惹き込まれる演出に思えたし、過去2回の映像化を踏まえて観るファンをねじ伏せようと言わんばかり力の入り様には脱帽。「物語はこれから」なので、最後まで見届けてどういう評価が下るのか、楽しみ。
折しもApple TV契約して「ファウンデーション」観始めたところなんだけど、しばらく「DUNE」の余韻に浸りたく、少し間を空けたほうがいいかなあ...なんて思っている。
非定期の甘いもの会、四人のメンバーのうちK女史が退社して実家に帰ることになったので、頑張ってねの開催。三越前の千疋屋で、四人とも季節のパフェ(は、栗)。話が弾む。
16 「高丘親王航海記」近藤ようこ(澁澤龍彦
原作)
「高丘親王航海記」近藤ようこ(澁澤龍彦
原作)2020年に第一巻が出た漫画化版、今週出た第四巻で完結した。原作に忠実、だけどキャラクターが近藤ようこの線で描かれることで、テキストを追うのとは異なる時間で話が動いているように感じた。原作の比較的シンプルだけど情報密度の高い(読み解こうとすると深さに驚く)異世界紀行とはまた違う、親王の感情の動きがより際立つ死生観を中心にしたストーリー。絵で表現された表情や視線が、空間的だったり内面的な広がりを生んでいることによるのだろう。読了後、しばし余韻に浸って動けず。
読んだ勢いで、ビリケンギャラリーでやっている原画展「南方奇譚」を見に行ってきた。在廊していた近藤先生にお願いして、第四巻の最終ページ(「完」の文字の横)にサインを戴く。明日で最終日ということもあって、お忙しそうでした。その後、ここまで一人で出てくることもなかなかないので、久しぶりの月光茶房。お忙しそうなところ、カウンターの末席にお邪魔してコーヒーを一杯。表参道は人出いっぱい。
 「台湾 四百年の歴史と展望」伊藤
潔
「台湾 四百年の歴史と展望」伊藤
潔1993年初版、自分が今回読んだのは26版(2020年)なので、長く読みつがれているのがよくわかる。実際、ポルトガルに"発見"されてから刊行直前まで(李登輝総裁二期目)の台湾史を11章にわけてわかりやすくまとめたもので、「自転車泥棒」「台湾海峡」を思い出しながら、彼の地の歴史大河が俯瞰できる。 著者は1937年台湾生、在命なら父と同じ歳(著者は2006年に逝去)..日本統治時代以降の語り口には我が親世代からのメッセージのようなものも感じる。短いが非常に思いが詰まった"あとがき"も、胸に迫る。「台湾海峡」には二・二八事件や戒厳令時代には触れられていないんだけど(「自転車泥棒」では二・二八事件は出てくる)、その時代をオープンに語れるまでにはなってないんだろうなあ...などと未だ続く複雑な政治・社会状況にも少し思い描いたり。断片的だった"台湾"の印象が、繋がって大きく更新されたように思う。奇しくも習近平の国家統一についての演説のタイミング、今後の動向から目が話せない。
 「台湾海峡 一九四九」龍應台(平野
健太郎 訳)
「台湾海峡 一九四九」龍應台(平野
健太郎 訳)原題「大江大海1949」、台湾での初版刊行は2009年、邦訳は2012年刊。「自転車泥棒」を切欠に、太平洋戦争前後のことを読みたくて...ということだったんだけど、本書によって、日中戦争から終戦..国共内戦の中で苛まれる人々について、さらに深く当時を知ることになった。大河ドキュメンタリーというわけではなく、本書を書くためのプロジェクトで収集した膨大な証言をもとに構成しており、著者の家族の話から始まって、国民党軍・解放軍の軍属、兵卒、日帝軍兵として戦った台湾人、その家族、学生、そして日帝軍人、豪・米兵などなど一人ひとりのストーリーに触れていくことで、混沌とした戦中戦後の台湾...のみならず中華民族の悲哀が浮かび上がる。教科書的な後付解釈による時代の整理とは異なる視点は、紋切り型の民族や国家の見方に対するアンチテーゼになってて、読み進めながら襟を正しつつ、近現代のアジアへの興味が湧き上がってきた。
突然の戦後を迎えたアフガニスタンを彷彿とさせるし、文化統制を強める昨今の習政権など、10年前の本だけど、リアルに今に対する示唆にも富んでいる。邦訳にあたって訳者による構成の調整などが施されたと訳者あとがきにあるが、丁寧な翻訳に感謝。良い本に巡り会えた。
台風接近後で昨日に続く晴天、夕富士見れるかなと夕方に出かける高尾山。16時前に高尾山口、琵琶滝から三号路経由で山頂17時過ぎ。雲に覆われ富士も日没も拝めず。微かな紫色に変わっていく空を少しの間眺めて下山は六号路。暗くなるなる中ヘッドランプを出そうと思ったら、忘れてやがる。iPhoneで足元を照らしながら、覚束ない足取り。18時半に駅着。10.44km、2時間50分、消費1,603kcal。帰宅途中に和泉多摩川駅下車、モスバーガーに寄って晩ごはん買う。国書刊行会のレム生誕100周年記念トートバッグとTシャツが届いてた。
02 「松本大洋本」小学館(漫画家本vol.4)
「松本大洋本」小学館(漫画家本vol.4)2018年刊のムック本。本人の長尺インタビュー、対談、評論、トリビュートに単行本未収録短編3作。amazonのオススメ。単行本未収録作も含めたこの当時までの作品リストを見ると、まあそこそこ読んでる気がする。すべてが好きな作品ではないし、少なくとも「花男」までは画が巧いとも思ってなかったんだけど(当時は、嫌いじゃなかったし、面白い絵だなーと思っていた)、大友克洋に憧れて...だったとは思わなかったなー。夏目房之介が「間に合った作家・松本大洋」で論じてる漫画出版の90年代末からの衰退に関する示唆は「東京ヒゴロ」に繋がってる。インタビューや対談の回想にも繋がりが見えて、続けて読んで正解。