29
 「自転車泥棒」呉明益(平野健太郎
訳)
「自転車泥棒」呉明益(平野健太郎
訳)
原題「The Stolen Bicycle」。2015年作で2018年のブッカー賞候補。最近文庫化されたらしいけど(カバー画の"あしらい"が異なってるみたい)、2018年の単行本で読む「複眼人」に続く2冊目の呉明益。少しノスタルジックで童話的なカバーとタイトルからは想像できない、重層的な大河ドラマ。自伝的な小説だけど、綿密なリサーチに基づいて丁寧に創られている。作者曰く「自転車を探すうち、意外な時間の流れに巻き込まれてしまう」のとおりで、前大戦を挟んだ父母の時代、台湾から東南アジアまでの地理的広がり、そもそも人間にとどまらないスケール...。記憶についての物語をビンテージ自転車の世界(てのがあるのも本書で知った)を使って創るってところが見事だし、登場人物たちの物語が色んな形でモザイク状に並んでいるので、読みすすめるだに時間と空間の感覚も混乱してくる虚実夢幻な展開が、非常に良質なミステリーでもある。個人的な自転車に纏わる記憶や、昨年逝った母の記憶が呼び起こされたりして、ここ数年でも特異的な読書体験でした。本書の中心である1940-50年代のモノローグは、今日のアフガニスタンの状況を彷彿とさせるところもあり、そういう意味でも普遍性を感じさせるところが凄い。原著は多言語で書かれているらしく、また訳者あとがきにもあるように丁寧な翻訳がなされてて、名訳にも感謝。
本書に合わせた2019年1月のインタビューが文春HPに掲載されているので、リンクを張っておく。それから作者あとがきでも触れられている台湾のビンテージ自転車店へのFacebook。
24
 「シルクロードとローマ帝国の興亡」井上文則
「シルクロードとローマ帝国の興亡」井上文則
今年の8月に出たばかり。先に読んできた蛮族とローマ帝国の話に中央アジアを絡めて...てところが期待だったんだけど、むしろ中国とインド、中東、ローマを繋ぐ海路の話。それはそれで面白く、ローマ帝国にとって絹やスパイス香料の輸入が如何に重要だったかという話と、ササン朝ペルシアの拡大が帝国の経済に影響を与えたのでわ?という問は興味深いと思う。のだけど、終盤の"ゲルマン民族の大移動"による帝国分裂と西ローマ帝国の衰亡のあたりは、昔の歴史観そのまま引用で興が醒めた。二次資料を中心に考察しているところも多く、全体的にも雑な印象。前半面白かったただけに、残念。
23
 「中世の異端者たち」甚野尚志
「中世の異端者たち」甚野尚志
「クローヴィス」読んでキリスト教の異端に興味が向いたので、amazonでいろいろ物色のうえこれをポチった。山川出版社の世界史リブレットシリーズって初購入だったんだけど、変形A5版サイズで90ページ弱、副読本的なものなのね。がっつり異端を分析解説してる200ページ強くらいをイメージしてたので、あれ?って感じだったけど、内容はアリウス派からルターまでを端的に解説してくれてて、ちょっと興味が...くらいの自分にはちょうど良かったかも。ヴァルド派、カタリ派、千年王国主義、自由心霊派の変遷というか連続性も簡単に社会政治情勢に触れながら教えてくれる、良書。いわゆる教科書的な宗教改革が数世紀に渡る「異端」の歴史の流れとして出てきたとことが分かったので、ルター派にも興味が。中世の、人々と宗教の関係への興味と言ってもよいかも。だけど、一度また古代末期に戻るつもり。
21
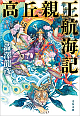 「高丘親王航海記」澁澤龍彦
「高丘親王航海記」澁澤龍彦
新装版で読む。近藤ようこの漫画版、10月に最終巻(第四巻)が出るということで、あらためて読んでおこうというわけ。説明不要の澁澤龍彦遺作。唐を出た親王が東南アジアを彷徨う...というか、夢と現の間を行き来する話。語り部は物語の外にいるようで、登場人物たちに異なる時間(現在)が混じり合う中で、物語の中にも融合していく。漫画ではどう描かれているのかなあ。四巻出たら一気に読もうと、表紙を捲らず待機中。
20
 「クローヴィス」ルネ・ミュソ=グラール(加納修
訳)
「クローヴィス」ルネ・ミュソ=グラール(加納修
訳)
メロヴィング朝フランク王国の初代の王でカトリックに改宗した最初の所謂"蛮族"王、の出自と一生、その影響を論じたもので1997年刊。「ゲルマン部族国家」と一緒に買ったもの。ローマ帝国末期から中世初期のガリアの様子を著したものでもある...んだけど、資料の少ないクローヴィスを、トゥール司教グレゴリウスの遺した記述を中心に論じているので、いかんせんカトリック教会側の見方に偏りすぎてて、読みながら引く...。カトリック教会が西欧における支配力を確立する成功体験が、ここで出来たんだろうということは判る。キリスト教内の教義をめぐる..あるいは教義にかこつけた闘争の発生初期も垣間見えて、そちらに興味が移る。ちなみに訳は読みにくい...というか原文がそもそも読解しにくいんじゃないかと思う。良い読者とは言えなかったなあ。先に「ゲルマン...」を読んでてよかった。
「ソラリス」のレム生誕100年記念カバー、出先の書店に入っても見つからなかったのは、ハヤカワ文庫の100冊フェア用だったからみたい。ってことで、新宿の紀伊國屋書店まで出かけて入手。
17
 「谷崎マンガ
- 変態アンソロジー」谷崎潤一郎 原作
「谷崎マンガ
- 変態アンソロジー」谷崎潤一郎 原作
短編マンガ集、イスパイアード・バイ・谷崎潤一郎。文庫化されたので早速。収録順に、久世番子、古屋兎丸、西村ツチカ、近藤聡乃、山田参助、今日マチ子、中村明日美子、榎本俊二、高野文子、しりあがり寿、山口晃。近藤X山口対談、古谷、中村のインタビュー、榎本の追加1篇、各者あとがき付き。谷崎よりもそれぞれの漫画家をもっと読みたくなるよ。近藤聡乃と山口晃がよかったので、探してみよう。大きく眺めたいので、単行本版(2016年)をポチる。マンガはkindleで!って決めてたつもりなのに、やっぱり紙の誘惑には勝てないいい。
大きなプレゼン2回目終了。いいのいいの、取り敢えずこれで説明責任は果たした。
15
 「マンガのあなた*SFのわたし」萩尾望都
「マンガのあなた*SFのわたし」萩尾望都
副題"萩尾望都対談集 1970年代"、2012年刊。BookOceanに預ける本を整理してたら出てきた。神保町三省堂のカバーがかかっているので、神保町勤務時代に書店購入したまま9年半積読に埋もれていたらしい。副題そのまま、76年から78年の対談と、本書のために行った羽海野チカとの対談を収録。手塚治虫、石森章太郎、水野英子、松本零士に小松左京...、寺山修司はつまんないが漫画家同士のやりとりは面白く読める。手塚、松本との三者対談は、萩尾のというより松本零士の独壇場みたいで、それはそれで愉しい(「大四畳半物語」の誕生秘話とか)。対談時期は「大泉の...」の時代よりも数年後だけど、溌溂としてて、竹宮恵子の翳は感じられないなあ。
13
 「短くて恐ろしいフィルの時代」ジョージ・ソーンダーズ(岸本佐和子
訳)
「短くて恐ろしいフィルの時代」ジョージ・ソーンダーズ(岸本佐和子
訳)
原題「The Brief and Frightning Reign of Phil」、2005年刊。邦訳は2011年、この間文庫化されてtwitter上で頻繁に見かけるのでポチった。河出文庫にはこの手で最近やられっぱなし。機械生命みたいなものが棲む世界で、外ホーナー国に囲まれた内ホーナー国の人口は6人。大きな外ホーナー国との国境問題に乗じて外ホーナー国人のフィルが台頭し、内ホーナー国を蹂躙するが...。チョビ髭の彼とホロコーストがすぐに浮かぶが、もっと一般化した寓話。結末はマクロには何ら問題解決がされてなく、結局は力の論理で短い平和が訪れる。そういう意味では、アフガニスタンを思い浮かべることも可能?(ちょっと違う気も)
12
 「ギケイキ2 奈落への飛翔」町田康
「ギケイキ2 奈落への飛翔」町田康
巻の弐。全巻最後の頼朝との初対面から、平家殲滅をすっ飛ばして、頼朝との対立、吉野落ちと静御前との別れまで。室町時代に創られた「義経記」の主人公としての義経が、実際のとこどうだったのかを回想するというややこしい物語構造。現在の倫理観と中世のそれのギャップやら、当時の政治情勢や地勢的な観点が、ふんだんに盛り込まれてて面白い。後半途中には「ザッツライトマスカラスネーク」なんて台詞がいきなりでてきて(つか、ザッツライトといえばマスカラスネークなんだが)、一体誰向けこの小説?
06
 「銀河帝国の興亡1 風雲編」アイザック・アシモフ(鍛治靖子
訳)
「銀河帝国の興亡1 風雲編」アイザック・アシモフ(鍛治靖子
訳)
ちょうど新刊の新訳ファウンデーションが届いたので、ローマ衰亡史の流れで早速読む。配信ドラマ化がスタートするので...ってことですよね。来年の春に3巻目が出る予定で、これからの楽しみ。小学生の頃、月の小遣い貰ったその足で近所の書店に走って1巻ずつ買って読んだのを思い出してる。読み直すのは随分久しぶりだけど、やっぱり面白いわー。「三体」の根っこにこれがあるのがよくわかる。巻末にこのシリーズの出自がまとめられてて、それも興味深い。あらためて、これが1940年代に書かれたということに驚きを禁じえない。(もともと連作として1942年から44年に書かれたものを1冊にまとめて一つの作品に仕上げたものがこの第一巻。) ドラマはApple TV+配信なんだけど、加入せんといかんのかなー。
05
 「ヨーロッパとゲルマン部族国家」マガリ・クメール、ブリューノ・デュメジル(大月康弘、小澤雄太郎
訳)
「ヨーロッパとゲルマン部族国家」マガリ・クメール、ブリューノ・デュメジル(大月康弘、小澤雄太郎
訳)
「エトルリア人」がローマ帝国形成期の(ローマから見た)夷狄の話だったのに対して、中期から後期以降のヨーロッパ形成史を、世界史教科書曰く"ゲルマン人の大移動"が現代の知見では時代遅れ...なところから地中海世界(ローマ帝国)に対する内陸部の夷狄(蛮族)の話として整理したもの。いわゆる"ゲルマン人"という言説が恣意的に用いられた20世紀については冒頭バッサリ斬った上で、2世紀から5世紀にかけての帝国と数々の蛮族との交流交雑の変遷、7世紀までの西ヨーロッパにおけるローマの消滅とキリスト教のもとでの王国の確立、特にガリアのローマ貴族が果たした役割、帝国の行政システムが継承されるあるいは聖職者として形を変えて残っていくところが、約150ページの中で端的にまとまってて、わかりやすく、高校生時分の知識から効率的にアップデートできて嬉しい。米軍のアフガニスタン撤収(Nation Buildingからの撤退)と世界秩序...みたいなところと合わせて考えてみたくなるなあ。本書は2010年に第一版が出たものが2016年に改訂第2版されたものを訳してるそうで、最新2018年第3版との差分も巻末についてます。訳注も丁寧で、よいお仕事をされてると感心。出てくる各蛮族についてもう少し知りたいんだけど、その辺は出てないのかな。
04
 「ギケイキ
- 千年の流転」町田康
「ギケイキ
- 千年の流転」町田康
巻の壱。弐巻目が文庫版で出たばっかりで、twitterで頻繁に目にする(フォローしている河出文庫がよくリツイートしてる)のにアテられて、では1巻目を読んでみようと。読みかけの本を置いて昨日届いたばかりの本書を読み始めたらあれよあれよと。「義経記」を現代で義経自身が書いたら...という体裁の町田版義経記現代訳。まずは頼朝との対面直前まで。こうして読むと、たしかにファッションについて矢鱈書いてるよね、とか、繋ぎキャラのその後については雑だよね、とか、(室町)当時のエンタメ譚のツボが際立つ。千年経っても変わらんのお...いや、もっとめんどくさくなってるやん世界、みたいなノリでテンポよく、あんまし残るものもなくサクッと読める。話題の2巻目もポチった。
午後3時間半のリモート研修会、PCつけっ放しにして散髪へ。時間の有効活用。さいとうたかお死去の報。ロニー・リストン・スミス死去の報。
26 「自転車泥棒」呉明益(平野健太郎
訳)
「自転車泥棒」呉明益(平野健太郎
訳)原題「The Stolen Bicycle」。2015年作で2018年のブッカー賞候補。最近文庫化されたらしいけど(カバー画の"あしらい"が異なってるみたい)、2018年の単行本で読む「複眼人」に続く2冊目の呉明益。少しノスタルジックで童話的なカバーとタイトルからは想像できない、重層的な大河ドラマ。自伝的な小説だけど、綿密なリサーチに基づいて丁寧に創られている。作者曰く「自転車を探すうち、意外な時間の流れに巻き込まれてしまう」のとおりで、前大戦を挟んだ父母の時代、台湾から東南アジアまでの地理的広がり、そもそも人間にとどまらないスケール...。記憶についての物語をビンテージ自転車の世界(てのがあるのも本書で知った)を使って創るってところが見事だし、登場人物たちの物語が色んな形でモザイク状に並んでいるので、読みすすめるだに時間と空間の感覚も混乱してくる虚実夢幻な展開が、非常に良質なミステリーでもある。個人的な自転車に纏わる記憶や、昨年逝った母の記憶が呼び起こされたりして、ここ数年でも特異的な読書体験でした。本書の中心である1940-50年代のモノローグは、今日のアフガニスタンの状況を彷彿とさせるところもあり、そういう意味でも普遍性を感じさせるところが凄い。原著は多言語で書かれているらしく、また訳者あとがきにもあるように丁寧な翻訳がなされてて、名訳にも感謝。
本書に合わせた2019年1月のインタビューが文春HPに掲載されているので、リンクを張っておく。それから作者あとがきでも触れられている台湾のビンテージ自転車店へのFacebook。
 「シルクロードとローマ帝国の興亡」井上文則
「シルクロードとローマ帝国の興亡」井上文則今年の8月に出たばかり。先に読んできた蛮族とローマ帝国の話に中央アジアを絡めて...てところが期待だったんだけど、むしろ中国とインド、中東、ローマを繋ぐ海路の話。それはそれで面白く、ローマ帝国にとって絹やスパイス香料の輸入が如何に重要だったかという話と、ササン朝ペルシアの拡大が帝国の経済に影響を与えたのでわ?という問は興味深いと思う。のだけど、終盤の"ゲルマン民族の大移動"による帝国分裂と西ローマ帝国の衰亡のあたりは、昔の歴史観そのまま引用で興が醒めた。二次資料を中心に考察しているところも多く、全体的にも雑な印象。前半面白かったただけに、残念。
 「中世の異端者たち」甚野尚志
「中世の異端者たち」甚野尚志「クローヴィス」読んでキリスト教の異端に興味が向いたので、amazonでいろいろ物色のうえこれをポチった。山川出版社の世界史リブレットシリーズって初購入だったんだけど、変形A5版サイズで90ページ弱、副読本的なものなのね。がっつり異端を分析解説してる200ページ強くらいをイメージしてたので、あれ?って感じだったけど、内容はアリウス派からルターまでを端的に解説してくれてて、ちょっと興味が...くらいの自分にはちょうど良かったかも。ヴァルド派、カタリ派、千年王国主義、自由心霊派の変遷というか連続性も簡単に社会政治情勢に触れながら教えてくれる、良書。いわゆる教科書的な宗教改革が数世紀に渡る「異端」の歴史の流れとして出てきたとことが分かったので、ルター派にも興味が。中世の、人々と宗教の関係への興味と言ってもよいかも。だけど、一度また古代末期に戻るつもり。
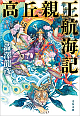 「高丘親王航海記」澁澤龍彦
「高丘親王航海記」澁澤龍彦新装版で読む。近藤ようこの漫画版、10月に最終巻(第四巻)が出るということで、あらためて読んでおこうというわけ。説明不要の澁澤龍彦遺作。唐を出た親王が東南アジアを彷徨う...というか、夢と現の間を行き来する話。語り部は物語の外にいるようで、登場人物たちに異なる時間(現在)が混じり合う中で、物語の中にも融合していく。漫画ではどう描かれているのかなあ。四巻出たら一気に読もうと、表紙を捲らず待機中。
長女の眼鏡買いに付き合って新宿のルミネエストまで(zoffに行った)。若者密度の濃さに頭痛が...。悪夢見そう。
19 「クローヴィス」ルネ・ミュソ=グラール(加納修
訳)
「クローヴィス」ルネ・ミュソ=グラール(加納修
訳)メロヴィング朝フランク王国の初代の王でカトリックに改宗した最初の所謂"蛮族"王、の出自と一生、その影響を論じたもので1997年刊。「ゲルマン部族国家」と一緒に買ったもの。ローマ帝国末期から中世初期のガリアの様子を著したものでもある...んだけど、資料の少ないクローヴィスを、トゥール司教グレゴリウスの遺した記述を中心に論じているので、いかんせんカトリック教会側の見方に偏りすぎてて、読みながら引く...。カトリック教会が西欧における支配力を確立する成功体験が、ここで出来たんだろうということは判る。キリスト教内の教義をめぐる..あるいは教義にかこつけた闘争の発生初期も垣間見えて、そちらに興味が移る。ちなみに訳は読みにくい...というか原文がそもそも読解しにくいんじゃないかと思う。良い読者とは言えなかったなあ。先に「ゲルマン...」を読んでてよかった。
「ソラリス」のレム生誕100年記念カバー、出先の書店に入っても見つからなかったのは、ハヤカワ文庫の100冊フェア用だったからみたい。ってことで、新宿の紀伊國屋書店まで出かけて入手。
 「谷崎マンガ
- 変態アンソロジー」谷崎潤一郎 原作
「谷崎マンガ
- 変態アンソロジー」谷崎潤一郎 原作短編マンガ集、イスパイアード・バイ・谷崎潤一郎。文庫化されたので早速。収録順に、久世番子、古屋兎丸、西村ツチカ、近藤聡乃、山田参助、今日マチ子、中村明日美子、榎本俊二、高野文子、しりあがり寿、山口晃。近藤X山口対談、古谷、中村のインタビュー、榎本の追加1篇、各者あとがき付き。谷崎よりもそれぞれの漫画家をもっと読みたくなるよ。近藤聡乃と山口晃がよかったので、探してみよう。大きく眺めたいので、単行本版(2016年)をポチる。マンガはkindleで!って決めてたつもりなのに、やっぱり紙の誘惑には勝てないいい。
大きなプレゼン2回目終了。いいのいいの、取り敢えずこれで説明責任は果たした。
午前中に大きなプレゼンを終えて(2回目が明後日なので荷はまだ肩に乗ったまま)、息抜きに日本橋でWと鮨食う。久しぶりの鮨はとても美味。2時間ほどゆっくり昼食というのも大変ヨロシイ。ついでに芋けんぴを列に並んで買う。Wと別れて日比谷まで歩いて戻ったらさすがに暑かった。仕事する気になんねーと文句言いつつ、結局オフィスを出たのは20時過ぎ。お土産の揚げたて芋けんぴ2袋は、アッという間に無くなる。
14 「マンガのあなた*SFのわたし」萩尾望都
「マンガのあなた*SFのわたし」萩尾望都副題"萩尾望都対談集 1970年代"、2012年刊。BookOceanに預ける本を整理してたら出てきた。神保町三省堂のカバーがかかっているので、神保町勤務時代に書店購入したまま9年半積読に埋もれていたらしい。副題そのまま、76年から78年の対談と、本書のために行った羽海野チカとの対談を収録。手塚治虫、石森章太郎、水野英子、松本零士に小松左京...、寺山修司はつまんないが漫画家同士のやりとりは面白く読める。手塚、松本との三者対談は、萩尾のというより松本零士の独壇場みたいで、それはそれで愉しい(「大四畳半物語」の誕生秘話とか)。対談時期は「大泉の...」の時代よりも数年後だけど、溌溂としてて、竹宮恵子の翳は感じられないなあ。
 「短くて恐ろしいフィルの時代」ジョージ・ソーンダーズ(岸本佐和子
訳)
「短くて恐ろしいフィルの時代」ジョージ・ソーンダーズ(岸本佐和子
訳)原題「The Brief and Frightning Reign of Phil」、2005年刊。邦訳は2011年、この間文庫化されてtwitter上で頻繁に見かけるのでポチった。河出文庫にはこの手で最近やられっぱなし。機械生命みたいなものが棲む世界で、外ホーナー国に囲まれた内ホーナー国の人口は6人。大きな外ホーナー国との国境問題に乗じて外ホーナー国人のフィルが台頭し、内ホーナー国を蹂躙するが...。チョビ髭の彼とホロコーストがすぐに浮かぶが、もっと一般化した寓話。結末はマクロには何ら問題解決がされてなく、結局は力の論理で短い平和が訪れる。そういう意味では、アフガニスタンを思い浮かべることも可能?(ちょっと違う気も)
 「ギケイキ2 奈落への飛翔」町田康
「ギケイキ2 奈落への飛翔」町田康巻の弐。全巻最後の頼朝との初対面から、平家殲滅をすっ飛ばして、頼朝との対立、吉野落ちと静御前との別れまで。室町時代に創られた「義経記」の主人公としての義経が、実際のとこどうだったのかを回想するというややこしい物語構造。現在の倫理観と中世のそれのギャップやら、当時の政治情勢や地勢的な観点が、ふんだんに盛り込まれてて面白い。後半途中には「ザッツライトマスカラスネーク」なんて台詞がいきなりでてきて(つか、ザッツライトといえばマスカラスネークなんだが)、一体誰向けこの小説?
 「銀河帝国の興亡1 風雲編」アイザック・アシモフ(鍛治靖子
訳)
「銀河帝国の興亡1 風雲編」アイザック・アシモフ(鍛治靖子
訳)ちょうど新刊の新訳ファウンデーションが届いたので、ローマ衰亡史の流れで早速読む。配信ドラマ化がスタートするので...ってことですよね。来年の春に3巻目が出る予定で、これからの楽しみ。小学生の頃、月の小遣い貰ったその足で近所の書店に走って1巻ずつ買って読んだのを思い出してる。読み直すのは随分久しぶりだけど、やっぱり面白いわー。「三体」の根っこにこれがあるのがよくわかる。巻末にこのシリーズの出自がまとめられてて、それも興味深い。あらためて、これが1940年代に書かれたということに驚きを禁じえない。(もともと連作として1942年から44年に書かれたものを1冊にまとめて一つの作品に仕上げたものがこの第一巻。) ドラマはApple TV+配信なんだけど、加入せんといかんのかなー。
 「ヨーロッパとゲルマン部族国家」マガリ・クメール、ブリューノ・デュメジル(大月康弘、小澤雄太郎
訳)
「ヨーロッパとゲルマン部族国家」マガリ・クメール、ブリューノ・デュメジル(大月康弘、小澤雄太郎
訳)「エトルリア人」がローマ帝国形成期の(ローマから見た)夷狄の話だったのに対して、中期から後期以降のヨーロッパ形成史を、世界史教科書曰く"ゲルマン人の大移動"が現代の知見では時代遅れ...なところから地中海世界(ローマ帝国)に対する内陸部の夷狄(蛮族)の話として整理したもの。いわゆる"ゲルマン人"という言説が恣意的に用いられた20世紀については冒頭バッサリ斬った上で、2世紀から5世紀にかけての帝国と数々の蛮族との交流交雑の変遷、7世紀までの西ヨーロッパにおけるローマの消滅とキリスト教のもとでの王国の確立、特にガリアのローマ貴族が果たした役割、帝国の行政システムが継承されるあるいは聖職者として形を変えて残っていくところが、約150ページの中で端的にまとまってて、わかりやすく、高校生時分の知識から効率的にアップデートできて嬉しい。米軍のアフガニスタン撤収(Nation Buildingからの撤退)と世界秩序...みたいなところと合わせて考えてみたくなるなあ。本書は2010年に第一版が出たものが2016年に改訂第2版されたものを訳してるそうで、最新2018年第3版との差分も巻末についてます。訳注も丁寧で、よいお仕事をされてると感心。出てくる各蛮族についてもう少し知りたいんだけど、その辺は出てないのかな。
 「ギケイキ
- 千年の流転」町田康
「ギケイキ
- 千年の流転」町田康巻の壱。弐巻目が文庫版で出たばっかりで、twitterで頻繁に目にする(フォローしている河出文庫がよくリツイートしてる)のにアテられて、では1巻目を読んでみようと。読みかけの本を置いて昨日届いたばかりの本書を読み始めたらあれよあれよと。「義経記」を現代で義経自身が書いたら...という体裁の町田版義経記現代訳。まずは頼朝との対面直前まで。こうして読むと、たしかにファッションについて矢鱈書いてるよね、とか、繋ぎキャラのその後については雑だよね、とか、(室町)当時のエンタメ譚のツボが際立つ。千年経っても変わらんのお...いや、もっとめんどくさくなってるやん世界、みたいなノリでテンポよく、あんまし残るものもなくサクッと読める。話題の2巻目もポチった。