27
 「バイオスフィア不動産」周藤蓮
「バイオスフィア不動産」周藤蓮
作者は第23回電撃小説大賞を受賞した方らしい。本作は描き下ろし連作で、バイオスフィアⅢ型建築という個人向け閉鎖環境住宅が一般化して、ほとんどの人々が"引き籠もり"となった未来世界を舞台にしたミステリ。閉所恐怖症でバイオスフィア住宅に住むことのできない少年と前大戦で負傷し脳神経組織の一部(とは書かれていないが)を除いて機械化された主人公、日本中のバイオスフィア住宅の保守を行う後香不動産のサービスコーディネーターである二人が、住宅からのクレーム解決を行うという話。全5話で完結。ウィズ・コロナの...というよりは、密室トリックの舞台を上手く作ったなあ...という感じ。SF要素はあまりないし、新世界を思弁するわけでもないが、ライトな奇想ミステリとして面白く読める。
早朝起床で4時キックオフのイングランド-米国戦を観たおかげで、体調リズムが狂っている。試合はといえば、米国のスピードにイングランドは固く守勢で対応という感じで、結局0-0のドロー。攻撃的なチーム相手だとイングランドは意外に攻撃下手?
24
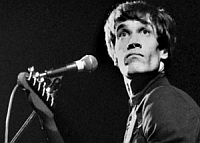 R.I.P.
Wilko Johnson
R.I.P.
Wilko Johnson
Jul 12, 1947 - Nov 21, 2022 (75)
1988年、トリオのライヴを天神ビブレホールで観た記憶(ブロックヘッズのノーマン・ワット・ロイ凄かったなあ...)。唯一無二。最高のロックンロール・ギター野郎。ウィルコ・ジョンソンいなかったら、アンディ・ギルのあのスタイルも無かったんじゃないかな。合掌。
23
 「もっと遠くへ行こう。」イアン・リード(坂本あおい
訳)
「もっと遠くへ行こう。」イアン・リード(坂本あおい
訳)
原題は「FOE」。前作長編はNetflix映画化で話題になったらしい。基本、ミステリ棚は(切りがないので)あたらないようにしてるんだけど、SF設定の異色ミステリってつぶやき見てポチってしまった。広大な畑の中の一軒家に住む夫婦のもとに謎の男が訪問してくる。主人公(夫氏)に、初めての宇宙移民のテスト移住者として選抜され、これから準備をすると告げられ...。基本この3人による舞台劇のような進行が、主人公の一人称視点で語られる。なにか大きな事件が起こるわけでもなく、淡々と、しかし孤立して住む夫婦間に闖入者が入ることでギクシャクとし始める日々の様子が繰り返し描かれる。まあ、オチは読めるし、意外性はないんだけど、空気と会話で少しづつ世界が変化していくところが文字でよく創られている。ホント舞台劇にしたら面白く脚本できるんじゃないでしょうか。値段に見合った面白さかというと、物足りん。
14
 R.I.P.
Keith Levene
R.I.P.
Keith Levene
Jul 18, 1957 - Nov 11, 2022 (65)
昨日、キース・レヴィン(綴からすれば"レヴァン"が正しい?)の訃報が流れてtwitterにもP.I.L.の映像が溢れた。肝臓癌を患っていたらしい。11月11日にノーフォークで死去、65歳。ポストパンク者にとって3大ギタリスト、最後のひとり(他の二人はアンディ・ギルとジョン・マッギオーク)。遺した音源は多くないけど、第一期P.I.L.でのプレイは永遠。
[1982年のMTVインタビュー | 1979年の"Check It Out"でのライヴ映像 | 1980年のTVインタビュー | Don Lettsの映像アーカイヴから初期PIL.映像 | 2013年?のインタビュー]
13

 「ザ・ブルー・ナイル 知られざる英国音楽の至宝」アラン・ブラウン(長山晃
訳)
「ザ・ブルー・ナイル 知られざる英国音楽の至宝」アラン・ブラウン(長山晃
訳)
原題は「The Blue Nile/ Nileism: The Strange Course」、2010年初版、で邦訳の本書は2011年のペーパーバック版を元にしているようです。長年のファンである長山氏が高じて訳出、DU Booksから昨年出たもので、プロ訳ではないですが読み易く、いやホントにありがたい。バンド結成に至る70年代末から2010年まで、4枚のアルバムが創られた経緯を中心に、寡作で知られるバンドの内情を描く。辿ってみれば、完全主義と(言い方悪いが)自意識過剰、バンド内力学の変化、複雑に絡む契約...という意外性のない話ではあるんだけど、グラスゴーのバンドというところがその個性の源であるというところは、コレ読むまでは意識しなかったです。ここ1週間ほど本書を読みながら、通勤の間アルバムを改めて聴いたり、書中出てくる音源や映像、さらに写真集などをチェックして、どっぷりハマってました。Hanging Around Booksから出てる1stアルバム発表直後の1984年に96年の3rdアルバムのレコ発ライブを少し載せた写真集を見てると、1stアルバムの頃の眩しさはやっぱり特別に思える。
*前身バンドであるMcIntyreの音源"Undercover"
*1stシングル"I Love This Life"
*1990年のUSツアードキュメンタリー"Flags and Fences"
The Blue Nileは一息ついて、ポストカード・レーベルを聴き返してみたくなってます。
12
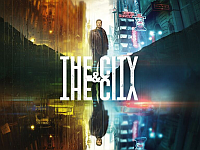 Prime
Videoで「都市と都市」(吹替版)。チャイナ・ミエヴェルの都市モノ代表作。BBCがTVドラマ化すると聞いたときは、どう映像化するんだろうと期待した。全5話、220分強。同じ土地に存在しながら片側からもう一方を認識してはいけないという特異な共存状態にある2都市国家を舞台にした殺人事件を、都市の狭間で妻が失踪し捜査打ち切りの過去を持つ刑事が捜査する。ドラマ版向けに設定の説明が親切にされるわけでもなく、原作読んでないとついていけないんじゃないかと心配。原作のファンとしては、映像化は巧く出来てると思うけど。ストーリーは、一つ一つのエピソードは原作に忠実だと思うんだけど、主人公の妻失踪への執着が主軸の構成で、こんな話だったっけか?と印象異なる。てことで、オチには納得いかなかったなあ。
Prime
Videoで「都市と都市」(吹替版)。チャイナ・ミエヴェルの都市モノ代表作。BBCがTVドラマ化すると聞いたときは、どう映像化するんだろうと期待した。全5話、220分強。同じ土地に存在しながら片側からもう一方を認識してはいけないという特異な共存状態にある2都市国家を舞台にした殺人事件を、都市の狭間で妻が失踪し捜査打ち切りの過去を持つ刑事が捜査する。ドラマ版向けに設定の説明が親切にされるわけでもなく、原作読んでないとついていけないんじゃないかと心配。原作のファンとしては、映像化は巧く出来てると思うけど。ストーリーは、一つ一つのエピソードは原作に忠実だと思うんだけど、主人公の妻失踪への執着が主軸の構成で、こんな話だったっけか?と印象異なる。てことで、オチには納得いかなかったなあ。
そういえば、「The Ring of Power」(2ndシーズンを早く!)でガラドリエル役のモーフィッド・クラークがヨランダ役で出ていてびっくり。
06
 「コンピューターが死んだ日」石原藤夫
「コンピューターが死んだ日」石原藤夫
1972年に光文社から初出の石原藤夫氏の第一長編、先日の神田古本まつりで買った中の徳間文庫83年版。国家プロジェクトで造られた東京湾沿岸の一大コンビナート群がある日突然爆発事故を起こし都内中枢を半壊させる。政府財界は事故直後から緊急の原因解明プロジェクトを秘密裏にスタートさせ、大企業仕事が合わず独立して情報技術コンサル業を営む主人公は知らずに末端の分析チームに雇われるのだが...。50年前に書かれたとは思えない、高度に情報化された社会の描写、ガジェットの的確な説明...携帯端末こそでてこないが、2020年代の今読んでコレはアレだ!と驚くばかり。政治に雇用、社会保障にそれこそ働き方など、描かれてる社会課題も身に覚えがあるものばかり。50年前のビジョンにようやく追いついたとも言えるし、問題すらそのまま実現してしまってるのに憂鬱にもなる。今日を確認するという意味でも、今再読するべき一冊。
05
 「ポロック生命体」瀬名秀明
「ポロック生命体」瀬名秀明
AIを主題にした2010年代の既出短編を再構成したもの。解説にも書いてある通り絵画についての生成系AIが界隈を賑わせてる今読まれるべき旬の一冊。2017年作の2編に続いて2012年の「きみによむ物語」、2019~20年に連載された表題作を収録、という構成でひとつの連作にも読める。作者が日本SF作家クラブ会長職を辞し退会する直前に書かれた「きみに...」があるので、ついつい呪詛めいたものを表題作にも見てしまうところはあるが、それは野暮なんでしょう。こうして並ぶと、知性とは?ヒトとは?というテーマに正面から向き合う瀬名氏らしさを全編に感じる。
何度目かのAIブーム到来と今のこの状況(生成系AIが物議になる)を2010年代後半に見通した表題作には、読みながら様々な思考がよぎり刺激になるが、創作者側・創作物からの目線がどちらかといえば支配的で、鑑賞者側と織りなすよりインタラクティブなシステムなどなど、自分が見たい思弁の先までもう少し。AIがヒトと種として分岐していくというイメージは出てきていて、この先を読みたいという読後感。駒を指す指先と音に着目する冒頭作「負ける」と表題作でのポロック画を再現するため画家の動き自体を再現するというアイデアの繋がりが、知性と身体性の関係を示唆して興味深い。[人間の輪郭、小説の輪郭 @新潮社]
04
 昼まで眠った文化の日。夕方Netflixで「オルタード・カーボン」(字幕版)を観始めたところ、結局10話一気に終わりまで観続ける羽目になる。観終わったのは深夜1時過ぎ。明日は...つか今日は出勤なのに。前半は原作と同じくハードボイルドな探偵モノ進行で謎が謎呼ぶ展開でついつい(忠実なのかは読んだのが随分前なので何ともいえないけど)、さてそろそろ真相解明編か?ってところで主人公の過去回想編に入って数話(この部分は蛇足だと思う)、後半一気に解決編に...ってところでやや水増し展開に冗長なエピローグ。AI、不死化、医療による貧富の分断、身体と魂(ゴースト)、面白くなりそうなネタは満載なんだけど、結局男女の"愛"が主題かよーって感じのオチには肩透かし(眠かったので、だらだら終わんなよーって気持ちもあった)。映像の作りは丁寧で、B級サイバーパンクにこれだけ気合い入れるとは!って一寸驚くレベル。ブレードランナーの世界観まんまですが、原作がそんな感じなので。
昼まで眠った文化の日。夕方Netflixで「オルタード・カーボン」(字幕版)を観始めたところ、結局10話一気に終わりまで観続ける羽目になる。観終わったのは深夜1時過ぎ。明日は...つか今日は出勤なのに。前半は原作と同じくハードボイルドな探偵モノ進行で謎が謎呼ぶ展開でついつい(忠実なのかは読んだのが随分前なので何ともいえないけど)、さてそろそろ真相解明編か?ってところで主人公の過去回想編に入って数話(この部分は蛇足だと思う)、後半一気に解決編に...ってところでやや水増し展開に冗長なエピローグ。AI、不死化、医療による貧富の分断、身体と魂(ゴースト)、面白くなりそうなネタは満載なんだけど、結局男女の"愛"が主題かよーって感じのオチには肩透かし(眠かったので、だらだら終わんなよーって気持ちもあった)。映像の作りは丁寧で、B級サイバーパンクにこれだけ気合い入れるとは!って一寸驚くレベル。ブレードランナーの世界観まんまですが、原作がそんな感じなので。
主人公役のヨエル・キナマンはなかなかハマっている。富裕者(不死者)女性役二人が美乳なのに対してヒロイン役他一般人役が豊満という対比は面白いなあ。
19時からは日本-コスタリカ戦。一方的な試合と思わせて、後半唯一のシュートで勝つコスタリカ、第一戦はスペインに7-0で敗退してるので必勝を期すアグレッシブなサッカーかと思いきや、終始固く守って唯一のチャンスをモノにする。結局諦めてなかったのはコスタリカの方だったという。0-1。いやー、我が事業の運営もこうありたい。
26 「バイオスフィア不動産」周藤蓮
「バイオスフィア不動産」周藤蓮作者は第23回電撃小説大賞を受賞した方らしい。本作は描き下ろし連作で、バイオスフィアⅢ型建築という個人向け閉鎖環境住宅が一般化して、ほとんどの人々が"引き籠もり"となった未来世界を舞台にしたミステリ。閉所恐怖症でバイオスフィア住宅に住むことのできない少年と前大戦で負傷し脳神経組織の一部(とは書かれていないが)を除いて機械化された主人公、日本中のバイオスフィア住宅の保守を行う後香不動産のサービスコーディネーターである二人が、住宅からのクレーム解決を行うという話。全5話で完結。ウィズ・コロナの...というよりは、密室トリックの舞台を上手く作ったなあ...という感じ。SF要素はあまりないし、新世界を思弁するわけでもないが、ライトな奇想ミステリとして面白く読める。
早朝起床で4時キックオフのイングランド-米国戦を観たおかげで、体調リズムが狂っている。試合はといえば、米国のスピードにイングランドは固く守勢で対応という感じで、結局0-0のドロー。攻撃的なチーム相手だとイングランドは意外に攻撃下手?
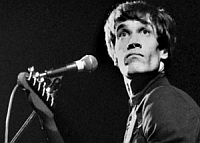 R.I.P.
Wilko Johnson
R.I.P.
Wilko JohnsonJul 12, 1947 - Nov 21, 2022 (75)
1988年、トリオのライヴを天神ビブレホールで観た記憶(ブロックヘッズのノーマン・ワット・ロイ凄かったなあ...)。唯一無二。最高のロックンロール・ギター野郎。ウィルコ・ジョンソンいなかったら、アンディ・ギルのあのスタイルも無かったんじゃないかな。合掌。
結局劇場で観なかった「シン・ウルトラマン」がPrime
Videoに出たので(最近TVCMでアピール喧しい)休日に観てすごす雨降りの勤労感謝の日。話を詰め込み過ぎなのか、カメラの切り替わり具合が好みじゃなかったからなのか、慌ただしさに、観終わったあとにあんまり印象残らず。最後に出てきたゼットンのラスボス感が今ひとつだったのもあるかなあ。個人的な好みとしては、メフィラス星人エピソードでもっと盛り上げて欲しかった。小ネタは満載で、オジサン的には背徳的で楽しめるけど、政治家ネタの絡め方は一寸中途半端だったかなあ。
んで、夜は日本時間10時キックオフのワールドカップ初戦のドイツ戦。2-1で勝利。相変わらず決定力ないドイツ、取った点も前半PK。日本はというと、後半の攻撃的布陣へのメンバーチェンジがハマって、後半2点で逆転勝利。ドイツに勝てるようになったのねー、と感慨深い。
19んで、夜は日本時間10時キックオフのワールドカップ初戦のドイツ戦。2-1で勝利。相変わらず決定力ないドイツ、取った点も前半PK。日本はというと、後半の攻撃的布陣へのメンバーチェンジがハマって、後半2点で逆転勝利。ドイツに勝てるようになったのねー、と感慨深い。
イングリッシュ・ブレックファストを食べよう!ということで、ランチは長女と日比谷に出かける。その後、来週85歳を迎える父への贈り物を探しに博品館まで。メジロのぬいぐるみを見つけたので、つがいで2羽買って送る。日比谷奥路地を歩いてみたけど、きれいなお店が並んでて楽しそうね。会社の会食なんかでは、銀座方面で店探すので、こっち側に足伸ばしたことはなかったなあ。
18
週3日呑みが2週続くと疲れが溜まる一方。
15 「もっと遠くへ行こう。」イアン・リード(坂本あおい
訳)
「もっと遠くへ行こう。」イアン・リード(坂本あおい
訳)原題は「FOE」。前作長編はNetflix映画化で話題になったらしい。基本、ミステリ棚は(切りがないので)あたらないようにしてるんだけど、SF設定の異色ミステリってつぶやき見てポチってしまった。広大な畑の中の一軒家に住む夫婦のもとに謎の男が訪問してくる。主人公(夫氏)に、初めての宇宙移民のテスト移住者として選抜され、これから準備をすると告げられ...。基本この3人による舞台劇のような進行が、主人公の一人称視点で語られる。なにか大きな事件が起こるわけでもなく、淡々と、しかし孤立して住む夫婦間に闖入者が入ることでギクシャクとし始める日々の様子が繰り返し描かれる。まあ、オチは読めるし、意外性はないんだけど、空気と会話で少しづつ世界が変化していくところが文字でよく創られている。ホント舞台劇にしたら面白く脚本できるんじゃないでしょうか。値段に見合った面白さかというと、物足りん。
 R.I.P.
Keith Levene
R.I.P.
Keith LeveneJul 18, 1957 - Nov 11, 2022 (65)
昨日、キース・レヴィン(綴からすれば"レヴァン"が正しい?)の訃報が流れてtwitterにもP.I.L.の映像が溢れた。肝臓癌を患っていたらしい。11月11日にノーフォークで死去、65歳。ポストパンク者にとって3大ギタリスト、最後のひとり(他の二人はアンディ・ギルとジョン・マッギオーク)。遺した音源は多くないけど、第一期P.I.L.でのプレイは永遠。
[1982年のMTVインタビュー | 1979年の"Check It Out"でのライヴ映像 | 1980年のTVインタビュー | Don Lettsの映像アーカイヴから初期PIL.映像 | 2013年?のインタビュー]

 「ザ・ブルー・ナイル 知られざる英国音楽の至宝」アラン・ブラウン(長山晃
訳)
「ザ・ブルー・ナイル 知られざる英国音楽の至宝」アラン・ブラウン(長山晃
訳)原題は「The Blue Nile/ Nileism: The Strange Course」、2010年初版、で邦訳の本書は2011年のペーパーバック版を元にしているようです。長年のファンである長山氏が高じて訳出、DU Booksから昨年出たもので、プロ訳ではないですが読み易く、いやホントにありがたい。バンド結成に至る70年代末から2010年まで、4枚のアルバムが創られた経緯を中心に、寡作で知られるバンドの内情を描く。辿ってみれば、完全主義と(言い方悪いが)自意識過剰、バンド内力学の変化、複雑に絡む契約...という意外性のない話ではあるんだけど、グラスゴーのバンドというところがその個性の源であるというところは、コレ読むまでは意識しなかったです。ここ1週間ほど本書を読みながら、通勤の間アルバムを改めて聴いたり、書中出てくる音源や映像、さらに写真集などをチェックして、どっぷりハマってました。Hanging Around Booksから出てる1stアルバム発表直後の1984年に96年の3rdアルバムのレコ発ライブを少し載せた写真集を見てると、1stアルバムの頃の眩しさはやっぱり特別に思える。
*前身バンドであるMcIntyreの音源"Undercover"
*1stシングル"I Love This Life"
*1990年のUSツアードキュメンタリー"Flags and Fences"
The Blue Nileは一息ついて、ポストカード・レーベルを聴き返してみたくなってます。
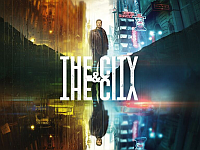 Prime
Videoで「都市と都市」(吹替版)。チャイナ・ミエヴェルの都市モノ代表作。BBCがTVドラマ化すると聞いたときは、どう映像化するんだろうと期待した。全5話、220分強。同じ土地に存在しながら片側からもう一方を認識してはいけないという特異な共存状態にある2都市国家を舞台にした殺人事件を、都市の狭間で妻が失踪し捜査打ち切りの過去を持つ刑事が捜査する。ドラマ版向けに設定の説明が親切にされるわけでもなく、原作読んでないとついていけないんじゃないかと心配。原作のファンとしては、映像化は巧く出来てると思うけど。ストーリーは、一つ一つのエピソードは原作に忠実だと思うんだけど、主人公の妻失踪への執着が主軸の構成で、こんな話だったっけか?と印象異なる。てことで、オチには納得いかなかったなあ。
Prime
Videoで「都市と都市」(吹替版)。チャイナ・ミエヴェルの都市モノ代表作。BBCがTVドラマ化すると聞いたときは、どう映像化するんだろうと期待した。全5話、220分強。同じ土地に存在しながら片側からもう一方を認識してはいけないという特異な共存状態にある2都市国家を舞台にした殺人事件を、都市の狭間で妻が失踪し捜査打ち切りの過去を持つ刑事が捜査する。ドラマ版向けに設定の説明が親切にされるわけでもなく、原作読んでないとついていけないんじゃないかと心配。原作のファンとしては、映像化は巧く出来てると思うけど。ストーリーは、一つ一つのエピソードは原作に忠実だと思うんだけど、主人公の妻失踪への執着が主軸の構成で、こんな話だったっけか?と印象異なる。てことで、オチには納得いかなかったなあ。そういえば、「The Ring of Power」(2ndシーズンを早く!)でガラドリエル役のモーフィッド・クラークがヨランダ役で出ていてびっくり。
 「コンピューターが死んだ日」石原藤夫
「コンピューターが死んだ日」石原藤夫1972年に光文社から初出の石原藤夫氏の第一長編、先日の神田古本まつりで買った中の徳間文庫83年版。国家プロジェクトで造られた東京湾沿岸の一大コンビナート群がある日突然爆発事故を起こし都内中枢を半壊させる。政府財界は事故直後から緊急の原因解明プロジェクトを秘密裏にスタートさせ、大企業仕事が合わず独立して情報技術コンサル業を営む主人公は知らずに末端の分析チームに雇われるのだが...。50年前に書かれたとは思えない、高度に情報化された社会の描写、ガジェットの的確な説明...携帯端末こそでてこないが、2020年代の今読んでコレはアレだ!と驚くばかり。政治に雇用、社会保障にそれこそ働き方など、描かれてる社会課題も身に覚えがあるものばかり。50年前のビジョンにようやく追いついたとも言えるし、問題すらそのまま実現してしまってるのに憂鬱にもなる。今日を確認するという意味でも、今再読するべき一冊。
 「ポロック生命体」瀬名秀明
「ポロック生命体」瀬名秀明AIを主題にした2010年代の既出短編を再構成したもの。解説にも書いてある通り絵画についての生成系AIが界隈を賑わせてる今読まれるべき旬の一冊。2017年作の2編に続いて2012年の「きみによむ物語」、2019~20年に連載された表題作を収録、という構成でひとつの連作にも読める。作者が日本SF作家クラブ会長職を辞し退会する直前に書かれた「きみに...」があるので、ついつい呪詛めいたものを表題作にも見てしまうところはあるが、それは野暮なんでしょう。こうして並ぶと、知性とは?ヒトとは?というテーマに正面から向き合う瀬名氏らしさを全編に感じる。
何度目かのAIブーム到来と今のこの状況(生成系AIが物議になる)を2010年代後半に見通した表題作には、読みながら様々な思考がよぎり刺激になるが、創作者側・創作物からの目線がどちらかといえば支配的で、鑑賞者側と織りなすよりインタラクティブなシステムなどなど、自分が見たい思弁の先までもう少し。AIがヒトと種として分岐していくというイメージは出てきていて、この先を読みたいという読後感。駒を指す指先と音に着目する冒頭作「負ける」と表題作でのポロック画を再現するため画家の動き自体を再現するというアイデアの繋がりが、知性と身体性の関係を示唆して興味深い。[人間の輪郭、小説の輪郭 @新潮社]
子会社の新工場施設竣工式で、出社会議後に川越へ。有楽町線から東武東上線を各駅停車で下りながら、沿線こんな感じなんやーと賃貸マンションの市価チェック。引っ越すならこっちもアリだなーと思いましたとさ。
03 昼まで眠った文化の日。夕方Netflixで「オルタード・カーボン」(字幕版)を観始めたところ、結局10話一気に終わりまで観続ける羽目になる。観終わったのは深夜1時過ぎ。明日は...つか今日は出勤なのに。前半は原作と同じくハードボイルドな探偵モノ進行で謎が謎呼ぶ展開でついつい(忠実なのかは読んだのが随分前なので何ともいえないけど)、さてそろそろ真相解明編か?ってところで主人公の過去回想編に入って数話(この部分は蛇足だと思う)、後半一気に解決編に...ってところでやや水増し展開に冗長なエピローグ。AI、不死化、医療による貧富の分断、身体と魂(ゴースト)、面白くなりそうなネタは満載なんだけど、結局男女の"愛"が主題かよーって感じのオチには肩透かし(眠かったので、だらだら終わんなよーって気持ちもあった)。映像の作りは丁寧で、B級サイバーパンクにこれだけ気合い入れるとは!って一寸驚くレベル。ブレードランナーの世界観まんまですが、原作がそんな感じなので。
昼まで眠った文化の日。夕方Netflixで「オルタード・カーボン」(字幕版)を観始めたところ、結局10話一気に終わりまで観続ける羽目になる。観終わったのは深夜1時過ぎ。明日は...つか今日は出勤なのに。前半は原作と同じくハードボイルドな探偵モノ進行で謎が謎呼ぶ展開でついつい(忠実なのかは読んだのが随分前なので何ともいえないけど)、さてそろそろ真相解明編か?ってところで主人公の過去回想編に入って数話(この部分は蛇足だと思う)、後半一気に解決編に...ってところでやや水増し展開に冗長なエピローグ。AI、不死化、医療による貧富の分断、身体と魂(ゴースト)、面白くなりそうなネタは満載なんだけど、結局男女の"愛"が主題かよーって感じのオチには肩透かし(眠かったので、だらだら終わんなよーって気持ちもあった)。映像の作りは丁寧で、B級サイバーパンクにこれだけ気合い入れるとは!って一寸驚くレベル。ブレードランナーの世界観まんまですが、原作がそんな感じなので。主人公役のヨエル・キナマンはなかなかハマっている。富裕者(不死者)女性役二人が美乳なのに対してヒロイン役他一般人役が豊満という対比は面白いなあ。