31
 「2010年
宇宙の旅」アーサー・C・クラーク(伊藤典夫 訳)
「2010年
宇宙の旅」アーサー・C・クラーク(伊藤典夫 訳)
2009年の新版(初回邦訳は94年)。ここまでは映画も観ている(多分リアルタイムで劇場で観てる)が、映画の記憶はロイ・シャイダーの顔くらいしかない。「2001年」の原作(小説版)は木星でフライバイして土星まで行ってたんだけど、これは映画の続編なので木星が舞台。最新の知見を元にしたハードSFとワイドスクリーンバロックな展開を違和感なく描ける人って、数多の作家の中でも、イーガンくらいしか思いつかない(あと小松左京か)。つか、イーガンも、クラークは越えれてないのかも...なんて思ったり。
22
 amazon.jpで5,100円なんて値が付いてるのを見ると、このタイミングで逝ってなかったら、どう評価されてたのかな...と、つい思ってしまう「★」。ギターアルバムではなくジャズ風ではあるけど、先端というわけでもなく。ピーター・ガブリエルぽかったり、最後の曲はちょっとユキヒロっぽいような。てか、やっぱりこの人の声力(コエヂカラ)って凄い。
14
amazon.jpで5,100円なんて値が付いてるのを見ると、このタイミングで逝ってなかったら、どう評価されてたのかな...と、つい思ってしまう「★」。ギターアルバムではなくジャズ風ではあるけど、先端というわけでもなく。ピーター・ガブリエルぽかったり、最後の曲はちょっとユキヒロっぽいような。てか、やっぱりこの人の声力(コエヂカラ)って凄い。
14
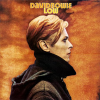
David Bowie
デヴィッド・ボウイの訃報(亡くなったのは10日)。帰宅して知る。熱心なファンだったことは一度もないけど、「Station to Station」は年に50回は聴いてる。ささやかながら追悼として久しぶりに「Low」を聴く。イーノ作のB面...とはいえ、"Subterranien"の後半のサックス、終盤のボーカルで一気に上るテンションに悶絶。その勢いで、公園ジョグ。我ながら意味不明の28分、4.08km、365kcal。帰宅して聴くのはやっぱり「Station to Station」、2010年に出た特装盤。2枚組のライヴが圧巻。カルロス・アロマーのギター鬼凄。
10
 New
Fast Automatic Daffodilsの"This is
Fascism"(Cinsolidatedのカバー)を冒頭に、リミックス14曲を2枚組で収録したもの。たまたまamazon.deで見つけて購入したら、日本から届いた。こんな盤があったとは知らなかったなあ。1996年リリース、アシッドテクノ!!
07
New
Fast Automatic Daffodilsの"This is
Fascism"(Cinsolidatedのカバー)を冒頭に、リミックス14曲を2枚組で収録したもの。たまたまamazon.deで見つけて購入したら、日本から届いた。こんな盤があったとは知らなかったなあ。1996年リリース、アシッドテクノ!!
07
 ピエール・ブーレーズが亡くなったとの報、クラシック・マニアな同僚二人が知らなかったのにちと驚いたが、バーデンバーデンに住んでたことを知らなかったのにさらに驚いた。新聞によっては一面に出てたくらい、ドイツでは大きなニュース。出社前と帰宅後に、InterContemporain(w/内村光子)によるモーツアルトとベルグのカップリング録音盤を聴く。
04
ピエール・ブーレーズが亡くなったとの報、クラシック・マニアな同僚二人が知らなかったのにちと驚いたが、バーデンバーデンに住んでたことを知らなかったのにさらに驚いた。新聞によっては一面に出てたくらい、ドイツでは大きなニュース。出社前と帰宅後に、InterContemporain(w/内村光子)によるモーツアルトとベルグのカップリング録音盤を聴く。
04
 「耳鼻削ぎの日本史」清水克行
「耳鼻削ぎの日本史」清水克行
2015年6月初版、休暇に入って買い集めた中世史本の最後の一冊。耳塚に関する柳田国男vs南方熊楠論争を導入にして、耳鼻削ぎ刑の出自と、室町・戦国期の展開、秀吉の朝鮮遠征から近世での消滅に至るまでを追う。生々しい事例の引用多く、それだけでも結構読ませる。少し強引な論旨もあるけど、元来は宥刑の位置づけだってという指摘、終章に出てくる中世日本は中国隣国型ではなく辺境型国家だったという話は、眼から鱗。
今回の休み中に由布岳でもと思って色々持参してたんだけど、折角の帰国、結局家族と過ごす時間優先してしまうよね。時差ボケも取れないし。毎回、行けるかもと思うんだけど、もう次からは止めよう。
単身赴任の辛さをしみじみ感じる、赴任先帰国翌日。
30
25日(月)、VIP御一行のヒアリングで玉砕。晩の駐在員との会食は一行宿傍のドイツ飯屋。26日(火)、夕方ぎりぎりまで打ち合わせ後、急いで空港へ向かい、東京出張。ほぼ眠って過ごしたフライト後、27日(水)の午後成田着、神保町の宿に入ってメール対応後、原宿方面はループウイラーへ出かけ、(昨年辞めてしまった)馴染みの店員氏にメールでお願いしていたブツを受け取りに。Scyeのスエットジャケット、サイズも丁度好い塩梅。神保町に戻って、同僚S氏と小料理屋で日本飯に舌鼓。28日(木)、出社。打ち合わせなどで一日が過ぎ、夜は米国駐在時代以来の知己I氏と、小料理屋。29日(金)、今回出張の本番、あっさり終了。夜は、バカ者どもが集まり、久しぶりの"男祭り"を中華屋で。久しぶりに死ぬほど笑って、宿に戻って一仕事。
てことで、今日フランクフルトに戻ってきた。ら、日本で使ってるiPhoneがない...探したところ、まだ成田空港に在るみたい...遠隔で紛失モードに。遺失物で届けられてるといいけど。 TeranishiのVentura、外ポケット完全に閉じられないのが一寸不安だったんだけど...当面一軍から外すことにする。
 「2061年
宇宙の旅」アーサー・C・クラーク(山高昭 訳)
「2061年
宇宙の旅」アーサー・C・クラーク(山高昭 訳)
2001年シリーズの設定使って当時の最新の知見を元に、彗星と木星衛星の探検譚を書いてみたかったとう感じで、前作までの巨視的な展開無く、良きハードSFといったところ。駄洒落で一本書いたって側面もありそうだけど、まあそれはよいとして、クラークの邦訳が、このレベルの訳で出版されてることに驚いた。堅い直訳風はまだ我慢するけど、明らかに前後の文章の繋がりおかしい所が散見、しまも結構致命的だったりして、興醒めすることしきり。
24てことで、今日フランクフルトに戻ってきた。ら、日本で使ってるiPhoneがない...探したところ、まだ成田空港に在るみたい...遠隔で紛失モードに。遺失物で届けられてるといいけど。 TeranishiのVentura、外ポケット完全に閉じられないのが一寸不安だったんだけど...当面一軍から外すことにする。
 「2061年
宇宙の旅」アーサー・C・クラーク(山高昭 訳)
「2061年
宇宙の旅」アーサー・C・クラーク(山高昭 訳)2001年シリーズの設定使って当時の最新の知見を元に、彗星と木星衛星の探検譚を書いてみたかったとう感じで、前作までの巨視的な展開無く、良きハードSFといったところ。駄洒落で一本書いたって側面もありそうだけど、まあそれはよいとして、クラークの邦訳が、このレベルの訳で出版されてることに驚いた。堅い直訳風はまだ我慢するけど、明らかに前後の文章の繋がりおかしい所が散見、しまも結構致命的だったりして、興醒めすることしきり。
風邪引いたみたい。鹿児島市に住んでる末弟からの大雪の報を受けたりしつつ、夕方までソファで毛布被って眠って過ごす。何とか起き上がって、週末送ると約束した資料を作る。夜は、明日からの欧州巡回で日本から御到着のVIP御一行(7名...って言葉通り大名行列)と会食で鮨元。22時半頃に帰宅し、資料を完成させ(まだ案ですが)、メールして薬をのむ。
23 「2010年
宇宙の旅」アーサー・C・クラーク(伊藤典夫 訳)
「2010年
宇宙の旅」アーサー・C・クラーク(伊藤典夫 訳)2009年の新版(初回邦訳は94年)。ここまでは映画も観ている(多分リアルタイムで劇場で観てる)が、映画の記憶はロイ・シャイダーの顔くらいしかない。「2001年」の原作(小説版)は木星でフライバイして土星まで行ってたんだけど、これは映画の続編なので木星が舞台。最新の知見を元にしたハードSFとワイドスクリーンバロックな展開を違和感なく描ける人って、数多の作家の中でも、イーガンくらいしか思いつかない(あと小松左京か)。つか、イーガンも、クラークは越えれてないのかも...なんて思ったり。
若手駐在O氏の人生相談でハウゼンの日本飯屋。天重を食う。
21
晩飯にポテチひと袋。胃が凭れてよく眠れない。
20
朝から夕方まで昼飯抜きで次から次へと、電話会議、ウェブ会議、ミーティングでぐったり。だけど会社の新年会、22時半まで。帰宅してから、日本時間の朝イチまでに送らないといけない報告書にもう一仕事。午前1時を過ぎると、今度は眠れなくなってしまう。
19
日中氷点下のフランクフルト。昨日は東京から出張の御一行とドイツ飯、今日はヴェニスから出張の御一行と日本飯。明日も夕食会だと思うと、気が重い...とはココにしか書けない。
16
たまに雪の降る夕方、12月から駐在している経理のM氏、着付け教室後のU嬢と、コンスタブラバッヘの飲茶中華屋...が満席だったので、その先のインド料理屋で、漫画について話す会。M氏は神戸大の漫研で評論担当だったということが判明。M嬢に薦めるSF本は何が良いか...て話から小川一水談義。次回は、他の若手駐在も入れて開催することを決め解散。
 ボウイとは無関係。今年はまず"宇宙の旅"シリーズを2001年から3001年までまとめ読みしようと言う訳で、まずは「2001年」を再読。93年に新訳(伊藤典夫)で出た決定版、冒頭に映画の制作と小説版を並行して書くに至った経緯(面白い)を収録。議論呼んだ終盤よりも冒頭の描写が丁寧になってることで、小説版は起結が結びつき、冒頭に説明のない映画版は難解になってしまった印象。しかし、初月面着陸前に、これを描き、撮れるものか。一行に含まれる先見性と情報量、含蓄に戦慄。(小説版の初版は1968年)
ボウイとは無関係。今年はまず"宇宙の旅"シリーズを2001年から3001年までまとめ読みしようと言う訳で、まずは「2001年」を再読。93年に新訳(伊藤典夫)で出た決定版、冒頭に映画の制作と小説版を並行して書くに至った経緯(面白い)を収録。議論呼んだ終盤よりも冒頭の描写が丁寧になってることで、小説版は起結が結びつき、冒頭に説明のない映画版は難解になってしまった印象。しかし、初月面着陸前に、これを描き、撮れるものか。一行に含まれる先見性と情報量、含蓄に戦慄。(小説版の初版は1968年)
15 ボウイとは無関係。今年はまず"宇宙の旅"シリーズを2001年から3001年までまとめ読みしようと言う訳で、まずは「2001年」を再読。93年に新訳(伊藤典夫)で出た決定版、冒頭に映画の制作と小説版を並行して書くに至った経緯(面白い)を収録。議論呼んだ終盤よりも冒頭の描写が丁寧になってることで、小説版は起結が結びつき、冒頭に説明のない映画版は難解になってしまった印象。しかし、初月面着陸前に、これを描き、撮れるものか。一行に含まれる先見性と情報量、含蓄に戦慄。(小説版の初版は1968年)
ボウイとは無関係。今年はまず"宇宙の旅"シリーズを2001年から3001年までまとめ読みしようと言う訳で、まずは「2001年」を再読。93年に新訳(伊藤典夫)で出た決定版、冒頭に映画の制作と小説版を並行して書くに至った経緯(面白い)を収録。議論呼んだ終盤よりも冒頭の描写が丁寧になってることで、小説版は起結が結びつき、冒頭に説明のない映画版は難解になってしまった印象。しかし、初月面着陸前に、これを描き、撮れるものか。一行に含まれる先見性と情報量、含蓄に戦慄。(小説版の初版は1968年) amazon.jpで5,100円なんて値が付いてるのを見ると、このタイミングで逝ってなかったら、どう評価されてたのかな...と、つい思ってしまう「★」。ギターアルバムではなくジャズ風ではあるけど、先端というわけでもなく。ピーター・ガブリエルぽかったり、最後の曲はちょっとユキヒロっぽいような。てか、やっぱりこの人の声力(コエヂカラ)って凄い。
amazon.jpで5,100円なんて値が付いてるのを見ると、このタイミングで逝ってなかったら、どう評価されてたのかな...と、つい思ってしまう「★」。ギターアルバムではなくジャズ風ではあるけど、先端というわけでもなく。ピーター・ガブリエルぽかったり、最後の曲はちょっとユキヒロっぽいような。てか、やっぱりこの人の声力(コエヂカラ)って凄い。
20時前に帰宅出来たので、公園ジョグ。
11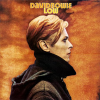
David Bowie
January 8, 1947 - January 10, 2016 (69)
デヴィッド・ボウイの訃報(亡くなったのは10日)。帰宅して知る。熱心なファンだったことは一度もないけど、「Station to Station」は年に50回は聴いてる。ささやかながら追悼として久しぶりに「Low」を聴く。イーノ作のB面...とはいえ、"Subterranien"の後半のサックス、終盤のボーカルで一気に上るテンションに悶絶。その勢いで、公園ジョグ。我ながら意味不明の28分、4.08km、365kcal。帰宅して聴くのはやっぱり「Station to Station」、2010年に出た特装盤。2枚組のライヴが圧巻。カルロス・アロマーのギター鬼凄。
週初めの時差ボケへの反動か、遅い起床。スカイプで進学相談。夕方に1周間ぶりのジョギング。往復3.9km、25分、消費347kcal、今日は三度目にして最も標準的なコース。YouTubeでバナナマン観てる間に終わる週末。
09 New
Fast Automatic Daffodilsの"This is
Fascism"(Cinsolidatedのカバー)を冒頭に、リミックス14曲を2枚組で収録したもの。たまたまamazon.deで見つけて購入したら、日本から届いた。こんな盤があったとは知らなかったなあ。1996年リリース、アシッドテクノ!!
New
Fast Automatic Daffodilsの"This is
Fascism"(Cinsolidatedのカバー)を冒頭に、リミックス14曲を2枚組で収録したもの。たまたまamazon.deで見つけて購入したら、日本から届いた。こんな盤があったとは知らなかったなあ。1996年リリース、アシッドテクノ!! ピエール・ブーレーズが亡くなったとの報、クラシック・マニアな同僚二人が知らなかったのにちと驚いたが、バーデンバーデンに住んでたことを知らなかったのにさらに驚いた。新聞によっては一面に出てたくらい、ドイツでは大きなニュース。出社前と帰宅後に、InterContemporain(w/内村光子)によるモーツアルトとベルグのカップリング録音盤を聴く。
ピエール・ブーレーズが亡くなったとの報、クラシック・マニアな同僚二人が知らなかったのにちと驚いたが、バーデンバーデンに住んでたことを知らなかったのにさらに驚いた。新聞によっては一面に出てたくらい、ドイツでは大きなニュース。出社前と帰宅後に、InterContemporain(w/内村光子)によるモーツアルトとベルグのカップリング録音盤を聴く。
早起きしてしまったので、引き続き近くの公園までジョギング33分、往復4.9kmで消費461kcal。雨降る夜道に公園内でちょっと道を間違え(出口を見逃し)危うく2周するところだった。帰宅7時。シャワー浴びて出勤。昼飯時から頭がボオッとしてくる。歳とともに時差ボケが辛くなるなあ。
03
早起きしてしまって手持ち無沙汰な朝、家族とスカイプ後に近くの公園までジョギング30分、往復4km強で消費407kcalは自転車通勤片道よりも燃焼多め。習慣にしたいが、果たして。腹減ったので、昼飯は、メッセ近くのラーメン屋まで自転車で。相変わらず並な味。
02
5時45分発のバスで大分空港へ、7時45分発のフライトで羽田空港着9時15分、バスで成田空港まで1時間半、12時15分発フランクフルト行きに搭乗、ほぼ眠って過ごして15時半過ぎに到着。タクシーで帰宅16時半。
 「紙の動物園」ケン・リュウ(古沢嘉通
訳)
「紙の動物園」ケン・リュウ(古沢嘉通
訳)
"多作なテッド・チャン"の日本オリジナル短編集。冒頭収録の表題作はSFなのか?という気もするが、ヒューゴー/ネヴュラ/世界幻想文学大賞のトリプル受賞...20頁に込められた祈りのようなもの。どの短編も中国からの移民米人作家ならではの歴史観や死生観が垣間見える"刺さる"話で、余韻を噛み締めながら丁寧に読む。ファンタジーからスチームパンクものに変貌する驚くべき"よい狩りを(Good Hunting)"を持ってくる構成も好い。アイデアの元ネタを各話末に注記するところなど、今様な理系作家らしく、スタンスもユニーク。もっと翻訳出して欲しいし、訳者解説で挙がってる中国SFもどんどん紹介して欲しいと思う。かつての光瀬龍的な雰囲気も漂う東洋的SFをもっと読んでみたい。
01 「紙の動物園」ケン・リュウ(古沢嘉通
訳)
「紙の動物園」ケン・リュウ(古沢嘉通
訳)"多作なテッド・チャン"の日本オリジナル短編集。冒頭収録の表題作はSFなのか?という気もするが、ヒューゴー/ネヴュラ/世界幻想文学大賞のトリプル受賞...20頁に込められた祈りのようなもの。どの短編も中国からの移民米人作家ならではの歴史観や死生観が垣間見える"刺さる"話で、余韻を噛み締めながら丁寧に読む。ファンタジーからスチームパンクものに変貌する驚くべき"よい狩りを(Good Hunting)"を持ってくる構成も好い。アイデアの元ネタを各話末に注記するところなど、今様な理系作家らしく、スタンスもユニーク。もっと翻訳出して欲しいし、訳者解説で挙がってる中国SFもどんどん紹介して欲しいと思う。かつての光瀬龍的な雰囲気も漂う東洋的SFをもっと読んでみたい。
 「耳鼻削ぎの日本史」清水克行
「耳鼻削ぎの日本史」清水克行2015年6月初版、休暇に入って買い集めた中世史本の最後の一冊。耳塚に関する柳田国男vs南方熊楠論争を導入にして、耳鼻削ぎ刑の出自と、室町・戦国期の展開、秀吉の朝鮮遠征から近世での消滅に至るまでを追う。生々しい事例の引用多く、それだけでも結構読ませる。少し強引な論旨もあるけど、元来は宥刑の位置づけだってという指摘、終章に出てくる中世日本は中国隣国型ではなく辺境型国家だったという話は、眼から鱗。
今回の休み中に由布岳でもと思って色々持参してたんだけど、折角の帰国、結局家族と過ごす時間優先してしまうよね。時差ボケも取れないし。毎回、行けるかもと思うんだけど、もう次からは止めよう。