30

 「さよならジュピター」小松左京
「さよならジュピター」小松左京
ハルキ文庫版上下二巻。なぜか最近目にすることが時々あって、小説版を読んだことないなあ...ってことでの今回。映画は公開当時観に行った記憶はあるけど、ほとんど覚えてないのよね。よくある三浦友和の尻の印象しかないってやつでw 小説版はノベライズではなく、「2001年」と同様、映画企画が先にあっての制作進行中に小説版を出す話になり...ということで、映画公開前に連載されている。単行本化が1982年で映画公開は1984年。映画製作の状況は上下巻各巻末に収録のインタビューで語られてて、映画自体の評価はともかく、作る側としてはかなり楽しんでいたみたい。(小説と同様修羅場であったのは想像に難くないが。) この小説版の解像度で映像化できてたら凄かったろうけど、当時の映画製作配給の状況(資金規模も含めて)や技術的な水準から考えれば、そもそも無理があったような気がする。太陽をブラックホールが直撃する"地球最後の日"を回避するため木星を使う...って話よりも、宇宙に進出する人間社会を想像してみたいというところに力点があって、出てくるテクノロジーも2020年代の今見ても的確...というか1980年代初めの想像力が現実のものになっているのも、未来の社会が現在の延長でありつつ来るべき変化は"そうであるべき"方向に向かっていることを現わしてるよう。まあ、80年代前半ならではの男女関係の描き方(なにかと肉食的)はキツイし陳腐なので、改めて再評価ってことにはならんだろうけど、その部分をバッサリ抜いてプロジェクトものSFとしてNetflixあたりでシリーズアニメ化できればかなり面白いと思う。終章最後に宇宙言語学者が垣間見る冷酷で不条理な宇宙への洞察が素晴らしく、これぞ小松左京の凄み。
現ハルキ文庫版は加藤直之カバーではなく、これはとても残念。
25
 DiscogでMagazineのLPに私の名前がクレジットされてるのを発見、イギリスから中古盤で購入してたものが、昨日帰宅したら届いてた。結局中古でなく未開封だったんだけど、この「Once
@The
Academy」、2016年のレコードストアデイで1,000枚限定で出たもの。再結成時に出たバイオ本に使われた私の写真が流用されたのでのクレジットということらしい。Magazineの音盤に、(マッギオークは居ないけど)メンバーに並んで名前がプリントされてるなんて、ファン冥利に尽きます。
DiscogでMagazineのLPに私の名前がクレジットされてるのを発見、イギリスから中古盤で購入してたものが、昨日帰宅したら届いてた。結局中古でなく未開封だったんだけど、この「Once
@The
Academy」、2016年のレコードストアデイで1,000枚限定で出たもの。再結成時に出たバイオ本に使われた私の写真が流用されたのでのクレジットということらしい。Magazineの音盤に、(マッギオークは居ないけど)メンバーに並んで名前がプリントされてるなんて、ファン冥利に尽きます。
今月に入って、Dans Les ArbresのというかHantsvilleのというか、Ivar Grydelandから突然、Flickrで日本ツアーの写真見たんだけどシェアしてくれない?ってメールが来たり、ファン冥利案件が続いている。
24
 「森のバルコニー」ジュリアン・グラック(中島昭和
訳)
「森のバルコニー」ジュリアン・グラック(中島昭和
訳)
グラックの4作目の小説。1981年に白水社から「狭い水路」と合わせて刊行されてたようです。今回、文遊社から訳者の遺したメモをもとに改訂版として出たもの。 アルデンヌの森にフランス軍が設置したトーチカに配属された士官が、近隣の村と森の間で過ごす日々、そして終盤、いよいよ戦争が始まり...。森の空気、匂い、湿度、陽の光と夜の闇、音、静けさ、時間の濃淡、そんなことが絶妙な比喩を重ねていきながら、主人公の心象として描写される。主観的な描写だからこそ生々しく森の中を体験している不思議な読書体験でした。突然現れ、戦争が迫ることでの心象の変化を象徴するような唐突な別れを迎える寡婦との短いエピソードが、古典的神話的な色合いを添えていて、余韻のある幕切れを迎える。山歩きの経験がないと文章から想起されるものはまったく違うんだろうけど、ヨーロッパの森が舞台のこの小説は、私にとってはハマりました。グラックはWW2での従軍で捕虜になった経験があり、その自伝的な話なのかと思ったんだけど、解説によればトーチカは本書を書くまで見たことはなかったらしい。とはいえ、「戦争」というものに対する市井の感覚を的確に写実しているのように思えます。
13
 「盧溝橋事件から日中戦争へ」岩谷將
「盧溝橋事件から日中戦争へ」岩谷將
帯に「なぜ局地紛争は全面戦争となったのか」とあるとおり、華北での現地軍間の紛争が全面戦争に変化していく過程を、基本的に日中双方の資料引用をもとに、北平、上海、南京の3章で追っている。特に北平の章では、衝突の経過と現地/中央のコミュニケーションや意思決定の経過が丹念に記述されていて、その擦れ違いの構図は全面戦争への移行を外交で解決しようとしていた上海/南京章でも繰り返される。実際、1937年7月から翌年1月までの話なんだよなあ。
予想通りにはいかない事態の進展のなか選択肢がなくなっていく過程は、結局は意思決定の遅さと大局感の喪失が意図せず後戻りできなくなっている状況を作っているようにも見えるし、すでに起こっている流れ(この場合は抗日、WW2前夜)には逆らいつつ想像されていた最悪の事態を回避しようとすることの難しさを改めて感じる。ここで一線を越えたことが現在の台湾に繋がっているのだし、ウクライナ紛争の表裏でも、ここに書かれているような動きが今もまさに為されているのだろうなあ...と、思いを馳せてみたり。大雑把で教科書数行的なストーリーと、ディテールを見ることでの理解の違いをあらためて考えるのも面白い。次は国共内戦について読んでみたいが。
08
 某中古レコード屋さんの呟きで飯島真理の2ndアルバムに清水靖晃参加と知って慌てて入手の「blanche」飯島真理。リン・ミンメイの人って認識で当時まったくチェックしてなかったけど、2ndは吉田美奈子プロデュースでバックはマライア面子。吉田美奈子ディレクションな楽曲・歌唱のキャラ付けに、当時のマライア、清水靖晃ソロワークの色濃いアレンジ。聴きごたえあり。飯島真理の声も嫌いじゃない。しかし吉田美奈子のバックコーラスの存在感たるや。
某中古レコード屋さんの呟きで飯島真理の2ndアルバムに清水靖晃参加と知って慌てて入手の「blanche」飯島真理。リン・ミンメイの人って認識で当時まったくチェックしてなかったけど、2ndは吉田美奈子プロデュースでバックはマライア面子。吉田美奈子ディレクションな楽曲・歌唱のキャラ付けに、当時のマライア、清水靖晃ソロワークの色濃いアレンジ。聴きごたえあり。飯島真理の声も嫌いじゃない。しかし吉田美奈子のバックコーラスの存在感たるや。
個人的な備忘のため、当時の(自分の中で)関連するアルバムを時系列に並べてみる。
「Light'n Up」吉田美奈子(1982)、「案山子」清水靖晃(1982)、「Rolling 80's」秋本奈緒美(1982)、「北京の秋」清水靖晃(1983)、「blanche」飯島真理(1984)、「音楽図鑑」坂本龍一(1984)
03
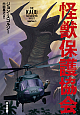 「怪獣保護協会」ジョン・スコルジー(内田昌之
訳)
「怪獣保護協会」ジョン・スコルジー(内田昌之
訳)
新型コロナ感染拡大のなかIT系サービス企業を解雇された主人公、ある縁でKRS(Kaiju Preservation Society):怪獣保護協会という団体で職を得ることに。新しい仕事先で知り合った就職同期の科学者たちと、怪獣についての探求を始めることになる...。"怪獣"のコンセプトが面白いし(想像する絵的にはゴジラよりはパシフィックリム...いやヘドラか)、なによりSFオタクならニヤリとするネタがそこかしこに出てきてて楽しい。オチも完璧。本書を書くに至った経緯が著者あとがきに書いてあって、これもまた面白い。まさに2021年だったからこそ書かれるべきだった作品といえるだろうし、時事的であり後世に何かを残す本と言っていいかも。いやまったく、作家というものは。訳者あとがきの最後に、主人公のジェンダーは?って問いがあって、「あー確かにー」と、そこでも一寸したセンスオブワンダーを感じている。
映画化に向いてると思う。サブスク系でシーズンドラマ化してもいいかも。

 「さよならジュピター」小松左京
「さよならジュピター」小松左京ハルキ文庫版上下二巻。なぜか最近目にすることが時々あって、小説版を読んだことないなあ...ってことでの今回。映画は公開当時観に行った記憶はあるけど、ほとんど覚えてないのよね。よくある三浦友和の尻の印象しかないってやつでw 小説版はノベライズではなく、「2001年」と同様、映画企画が先にあっての制作進行中に小説版を出す話になり...ということで、映画公開前に連載されている。単行本化が1982年で映画公開は1984年。映画製作の状況は上下巻各巻末に収録のインタビューで語られてて、映画自体の評価はともかく、作る側としてはかなり楽しんでいたみたい。(小説と同様修羅場であったのは想像に難くないが。) この小説版の解像度で映像化できてたら凄かったろうけど、当時の映画製作配給の状況(資金規模も含めて)や技術的な水準から考えれば、そもそも無理があったような気がする。太陽をブラックホールが直撃する"地球最後の日"を回避するため木星を使う...って話よりも、宇宙に進出する人間社会を想像してみたいというところに力点があって、出てくるテクノロジーも2020年代の今見ても的確...というか1980年代初めの想像力が現実のものになっているのも、未来の社会が現在の延長でありつつ来るべき変化は"そうであるべき"方向に向かっていることを現わしてるよう。まあ、80年代前半ならではの男女関係の描き方(なにかと肉食的)はキツイし陳腐なので、改めて再評価ってことにはならんだろうけど、その部分をバッサリ抜いてプロジェクトものSFとしてNetflixあたりでシリーズアニメ化できればかなり面白いと思う。終章最後に宇宙言語学者が垣間見る冷酷で不条理な宇宙への洞察が素晴らしく、これぞ小松左京の凄み。
現ハルキ文庫版は加藤直之カバーではなく、これはとても残念。
 DiscogでMagazineのLPに私の名前がクレジットされてるのを発見、イギリスから中古盤で購入してたものが、昨日帰宅したら届いてた。結局中古でなく未開封だったんだけど、この「Once
@The
Academy」、2016年のレコードストアデイで1,000枚限定で出たもの。再結成時に出たバイオ本に使われた私の写真が流用されたのでのクレジットということらしい。Magazineの音盤に、(マッギオークは居ないけど)メンバーに並んで名前がプリントされてるなんて、ファン冥利に尽きます。
DiscogでMagazineのLPに私の名前がクレジットされてるのを発見、イギリスから中古盤で購入してたものが、昨日帰宅したら届いてた。結局中古でなく未開封だったんだけど、この「Once
@The
Academy」、2016年のレコードストアデイで1,000枚限定で出たもの。再結成時に出たバイオ本に使われた私の写真が流用されたのでのクレジットということらしい。Magazineの音盤に、(マッギオークは居ないけど)メンバーに並んで名前がプリントされてるなんて、ファン冥利に尽きます。今月に入って、Dans Les ArbresのというかHantsvilleのというか、Ivar Grydelandから突然、Flickrで日本ツアーの写真見たんだけどシェアしてくれない?ってメールが来たり、ファン冥利案件が続いている。
20日の朝、夜中に酸素濃度低下し呼吸が浅いとの連絡が、父が入っている介護施設からあり、弟達に連絡して今日中に帰省するよう指示、私もJAL最終便でかみさんと宮崎へ。21日朝に心肺停止の連絡を宿で受け、施設へ向かう。9時過ぎに到着したら、ちょうどかかりつけの在宅クリニック医師先生が死亡を確認したところでした。一緒についた三男と確認。闘病の苦しさから解放されたような安らかな眠っているような顔。ってことで、母の葬儀をしてもらった家族葬のファミーユに連絡。その時と同じホールで葬儀をあげる段取り。夕方に一時安置してた別のホールから遺体が到着。通夜葬儀の打ち合わせ。翌日は朝に湯灌の儀、通夜は夕方。22日は葬儀告別式、火葬、初七日。実家に戻ったのは16時ごろだったかな。骨壺を納めて解散。宿に帰って夫婦でぐったり。そんなわけで今朝発の便で飛び、帰宅結局13時半ごろ。ちょっと休んで散髪に行った。
世帯主の変更、銀行口座(なんかいっぱいあるし)、年金に保険、それからもちろん相続関係...手続きが山と待っていそうで、早速げんなりしている。できれば年内に全部片付けてしまいたい。
16世帯主の変更、銀行口座(なんかいっぱいあるし)、年金に保険、それからもちろん相続関係...手続きが山と待っていそうで、早速げんなりしている。できれば年内に全部片付けてしまいたい。
 「森のバルコニー」ジュリアン・グラック(中島昭和
訳)
「森のバルコニー」ジュリアン・グラック(中島昭和
訳)グラックの4作目の小説。1981年に白水社から「狭い水路」と合わせて刊行されてたようです。今回、文遊社から訳者の遺したメモをもとに改訂版として出たもの。 アルデンヌの森にフランス軍が設置したトーチカに配属された士官が、近隣の村と森の間で過ごす日々、そして終盤、いよいよ戦争が始まり...。森の空気、匂い、湿度、陽の光と夜の闇、音、静けさ、時間の濃淡、そんなことが絶妙な比喩を重ねていきながら、主人公の心象として描写される。主観的な描写だからこそ生々しく森の中を体験している不思議な読書体験でした。突然現れ、戦争が迫ることでの心象の変化を象徴するような唐突な別れを迎える寡婦との短いエピソードが、古典的神話的な色合いを添えていて、余韻のある幕切れを迎える。山歩きの経験がないと文章から想起されるものはまったく違うんだろうけど、ヨーロッパの森が舞台のこの小説は、私にとってはハマりました。グラックはWW2での従軍で捕虜になった経験があり、その自伝的な話なのかと思ったんだけど、解説によればトーチカは本書を書くまで見たことはなかったらしい。とはいえ、「戦争」というものに対する市井の感覚を的確に写実しているのように思えます。
喉の違和感を訴えていた父の胃カメラ検査への付き添いで帰省のはずが、週明けに誤嚥性肺炎が発覚して熱発・酸素吸入が始まったため、検査は見送り、かかりつけクリニックと施設の看護師介護士の方々とのミーティングに変更。居室に父を見舞うが、肺炎の具合は深刻そう。そのあと実家によって午後のリモート会議に備えようとしたところ、家の鍵を次男が大阪に持ってってることが判明。あきらめて宮崎駅に戻り、近くのカラオケボックスで会議をこなす。帰りの飛行機は案の定遅延(といっても30分くらいですが...しかし定刻に飛んだことがほとんどないよね)。帰宅したら、白水社から在庫僅少本フェアでの購書が届いてた(勢いで買ってしまった「アラビア書道の宇宙」は要らんかったかー)。宮崎も水中歩いてるみたいな湿度だったけど、戻ってきた東京も蒸すね。
10
PC自作メモ(続)。
computer-1で組み立てたPC、ケース専用のフロントパネルオーディオポートで音出力ができず色々接続を弄ってみたものの解決できない。ってことで、現在はマザーボードに配線せず死んだ状態にしています。暇なんでYoutubeでcomputer-1組んだ動画s眺めてたら、これに関する質問が載ってるものを発見。RealtekのHDオーディオコーデックをインストールて解決したとのこと。ちなみに接続は、S→GND、T→PORT2L、R→PORT2R。これ、結構困ってる人多そうなのに、解決策を書いてあるとこって出てこないし、そもそも困ってるって話も表にはなかなか出ていないのね。皆さんどうしてるのかしら。
09computer-1で組み立てたPC、ケース専用のフロントパネルオーディオポートで音出力ができず色々接続を弄ってみたものの解決できない。ってことで、現在はマザーボードに配線せず死んだ状態にしています。暇なんでYoutubeでcomputer-1組んだ動画s眺めてたら、これに関する質問が載ってるものを発見。RealtekのHDオーディオコーデックをインストールて解決したとのこと。ちなみに接続は、S→GND、T→PORT2L、R→PORT2R。これ、結構困ってる人多そうなのに、解決策を書いてあるとこって出てこないし、そもそも困ってるって話も表にはなかなか出ていないのね。皆さんどうしてるのかしら。
 「盧溝橋事件から日中戦争へ」岩谷將
「盧溝橋事件から日中戦争へ」岩谷將帯に「なぜ局地紛争は全面戦争となったのか」とあるとおり、華北での現地軍間の紛争が全面戦争に変化していく過程を、基本的に日中双方の資料引用をもとに、北平、上海、南京の3章で追っている。特に北平の章では、衝突の経過と現地/中央のコミュニケーションや意思決定の経過が丹念に記述されていて、その擦れ違いの構図は全面戦争への移行を外交で解決しようとしていた上海/南京章でも繰り返される。実際、1937年7月から翌年1月までの話なんだよなあ。
予想通りにはいかない事態の進展のなか選択肢がなくなっていく過程は、結局は意思決定の遅さと大局感の喪失が意図せず後戻りできなくなっている状況を作っているようにも見えるし、すでに起こっている流れ(この場合は抗日、WW2前夜)には逆らいつつ想像されていた最悪の事態を回避しようとすることの難しさを改めて感じる。ここで一線を越えたことが現在の台湾に繋がっているのだし、ウクライナ紛争の表裏でも、ここに書かれているような動きが今もまさに為されているのだろうなあ...と、思いを馳せてみたり。大雑把で教科書数行的なストーリーと、ディテールを見ることでの理解の違いをあらためて考えるのも面白い。次は国共内戦について読んでみたいが。
 某中古レコード屋さんの呟きで飯島真理の2ndアルバムに清水靖晃参加と知って慌てて入手の「blanche」飯島真理。リン・ミンメイの人って認識で当時まったくチェックしてなかったけど、2ndは吉田美奈子プロデュースでバックはマライア面子。吉田美奈子ディレクションな楽曲・歌唱のキャラ付けに、当時のマライア、清水靖晃ソロワークの色濃いアレンジ。聴きごたえあり。飯島真理の声も嫌いじゃない。しかし吉田美奈子のバックコーラスの存在感たるや。
某中古レコード屋さんの呟きで飯島真理の2ndアルバムに清水靖晃参加と知って慌てて入手の「blanche」飯島真理。リン・ミンメイの人って認識で当時まったくチェックしてなかったけど、2ndは吉田美奈子プロデュースでバックはマライア面子。吉田美奈子ディレクションな楽曲・歌唱のキャラ付けに、当時のマライア、清水靖晃ソロワークの色濃いアレンジ。聴きごたえあり。飯島真理の声も嫌いじゃない。しかし吉田美奈子のバックコーラスの存在感たるや。個人的な備忘のため、当時の(自分の中で)関連するアルバムを時系列に並べてみる。
「Light'n Up」吉田美奈子(1982)、「案山子」清水靖晃(1982)、「Rolling 80's」秋本奈緒美(1982)、「北京の秋」清水靖晃(1983)、「blanche」飯島真理(1984)、「音楽図鑑」坂本龍一(1984)
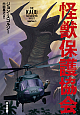 「怪獣保護協会」ジョン・スコルジー(内田昌之
訳)
「怪獣保護協会」ジョン・スコルジー(内田昌之
訳)新型コロナ感染拡大のなかIT系サービス企業を解雇された主人公、ある縁でKRS(Kaiju Preservation Society):怪獣保護協会という団体で職を得ることに。新しい仕事先で知り合った就職同期の科学者たちと、怪獣についての探求を始めることになる...。"怪獣"のコンセプトが面白いし(想像する絵的にはゴジラよりはパシフィックリム...いやヘドラか)、なによりSFオタクならニヤリとするネタがそこかしこに出てきてて楽しい。オチも完璧。本書を書くに至った経緯が著者あとがきに書いてあって、これもまた面白い。まさに2021年だったからこそ書かれるべきだった作品といえるだろうし、時事的であり後世に何かを残す本と言っていいかも。いやまったく、作家というものは。訳者あとがきの最後に、主人公のジェンダーは?って問いがあって、「あー確かにー」と、そこでも一寸したセンスオブワンダーを感じている。
映画化に向いてると思う。サブスク系でシーズンドラマ化してもいいかも。